| 先月の この一曲 | |||
|
●最近の「個人的な」お気に入りの音楽に関して (読書に関しては日記のほうにに書くことにしました。すみません(^^;;) ●最新の「今月の一曲」へもどる |
ニーナ・シモン(キングレコード - ASIN: B00005F7DF)\1714(税込) ---------------------------------------------------------- ■ さよなら、ニーナ・シモン ■ ---------------------------------------------------------- ●つい、このあいだの4月21日、偉大なる黒人女性歌手 ニーナ・シモンが死んだ。 ぼくも大好きなニーナ・シモンに関しては、以前から既に、 「さとなお」さんの「ソウルの世界」に関する熱い文章 や、 こんなところの文章 など、決定的なものが出てはいるのですが、この際、ぼくにも一言、書かせてください。 ●ぼくは、綾戸智絵がピアノの弾き語りで『ミスター・ボージャングル』 を歌っているのを初めて聴いたとき、「あっ、この人は日本のニーナ・シモンだ!」そう思ったんです。最近の人気女性ジャズ・ヴォーカルは、みな「ピアノの弾き語り」 ができます。ダイアナ・クラールしかり、綾戸智絵しかり、ケイコ・リーしかり。 いや、最近に限らず、ぼくの好みの女性ヴォーカルはみな(例えば、カーメン・マックレー、それから、ブロッサム・ディアリー(^^;))ピアノの弾き語りにおいてこそ、その魅力が一番きらめく人ばかりなのです。 そして、ニーナ・シモンもまた「弾き語りの人」でした。そんな彼女の最大限の魅力が発揮され、アルバムとしてのトータルなバランスも完璧なCDはと言うと、自演のピアノだけをバックに歌った『ソウルの世界』であることは、大方の認めるところです。 ところが、ぼくが先日、彼女の死を追悼するためにプレーヤーのターンテーブルに載っけたのは、じつは『ソウルの世界』ではありませんでした。実際にかけたレコードは、この『ボルチモア』A面だったのです。アルバム・コンセプトの統一性としては『ソウルの世界』よりも劣っているかもしれないけれど、『ボルチモア』A面1曲目、2曲目と続く超強力なラインナップのすごさには、どのアルバムも敵わないからです。 とにかく、2曲目の「Everything Must Change」の絶唱を聴いてみて下さい。ぼくは、この曲を聴くたびに、中島みゆきの歌(タイトル忘れた)「かわらないものた〜ち〜の…」というフレーズを思い出します。世の中どんどん変わってゆく中で、どうにも変わらない自分がいて、そんな自分と世間とが折り合いが会わずにとことん落ち込んだとき、よくこの曲を聴きました。何度も何度も。 暗い歌ですが、ニーナ・シモンの歌声には確信的な力強さがあって、「だいじょうぶ、だいじょうぶ、ちゃんとやってゆけるさ!」って、ぼくを励ましてくれるのです。そうやって、ぼくは何度もニーナ・シモンに助けられてきたのでした。 ありがとう、ニーナ・シモン。 (2003年04月25日 記) |
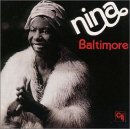 ニーナ・シモン (キング - ASIN: B00005F7DF) |
波多野睦美(歌)つのだたかし(ギター・リュート)( ワーナーミュージック・ジャパン/ WPCS-11475)\2520(税込) ---------------------------------------------------------- ■静謐でメランコリックで懐かしい音楽: 武満徹「小さな空」がとにかく素晴らしい! ---------------------------------------------------------- ●リュート奏者のつのだたかしが主宰する、中世ヨーロッパの古楽器を専門に演奏する不思議なアンサンブル「タブラトゥーラ」 のCD『蟹』を持っていたので、『CDジャーナル』にこの『アルフォンシーナと海』が新譜として紹介されているのを「おっ!?」と思って見ました。黒田恭一さんも<こんなふうに>このCDを紹介していて、先だって上京した際に、銀座山野楽器で見つけて買ってきました。 聴いてみてビックリしたのは、つのだたかしはリュートではなくて「ギター」を弾いていたことと、中世ルネッサンスの作曲家の楽曲ではなく、20世紀の現代音楽で統一されていたことです。前半はアルゼンチン・ブラジルといった南米の作曲家の作品、後半には、ラヴェル、プーラング、ラルフ・ヴォーン・ウイリアムズ、そして武満徹の作品がならびます。 この選曲と曲の配列の妙が、じつに巧みに企てられていて、聴きながら何の違和感もなく、ブエノスアイレス→ リオ・デ・ジャネイロ→ パリ→ ロンドン→ 東京へと心地よく誘(いざな)われてゆくのです。 波多野睦美の澄んだ、よく通る歌声は、バロック以前の宗教音楽のボーイ・ソプラノのような中性的な響きがあって、決して今風の楽曲には合わない声質だと思うし、ましてやぜんぜん違う声である「アルフォンシーナと海」のメルセデス・ソーサや、ピアソラとの共演で「忘却」を歌うカンツォーネの大御所ミルヴァといった決定的名唱がある、その曲にあえてチャレンジしているので、当初はオリジナルとの雰囲気の違いにとまどってしまったんだけれども、聞き込むうちに、つのだたかしのギター伴奏とともに、不思議と妙にしっくりなじんでくるのです。 そうして、ただ「うっとりと」この二人のデュオに身をゆだねて聴いていると、突然日本語の歌詞が耳に飛び込んできてビックリします。それが、武満徹「小さな空」なのです。これが凄い! ぼくは今回初めて聴いた曲なのですが、あまりに懐かしくて、思わず涙があふれてきました。なんといういい詩・いい曲なんでしょう! こんなにもシンプルな楽曲なのに。この曲が、このCDのベストだと思います、たぶん。1960年代の武満徹自身による作詞作曲だそうです。ラストは谷川俊太郎の詩に武満徹が曲をつけた「三月のうた」ですが、つのだたかしは、この曲だけギターではなくリュートを弾いています。この曲も、じつにいい詩だなぁ。 (2003年03月20日 記) ところで、つのだたかしさんて、やっぱし、つのだじろう・つのだひろ・三兄弟の一人だったのですね(^^;; (2003年03月30日 記) |
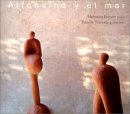 波多野睦美・つのだたかし (ワーナー/WPCS-11475) 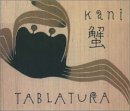 タブラトゥーラ (ワーナー/WPCS-10462) |
押尾コータロー『STARTING POINT』(東芝EMI / TOCT-24820)\3000(税込) 2002/07/10 発売 ---------------------------------------------------- ■驚異のアコースティック・ギター、ソロ・インスト・アルバム■ ---------------------------------------------------- ●押尾コータローのギターを初めて聴いたのは、FMラジオの「HILL SIDE アベニュー」かなにかにゲスト出演した時で、たしかその中で「戦場のメリークリスマス」がオンエアーされたのです。びっくりしました。ギター・ソロで、しかも多重録音は一切なしなのに、まるでオーケストレーションされたかのような重厚で奥行きのあるサウンドが繰り広げられていて、とても、ギター・ソロの一発ライヴ録りの演奏とは思えませんでした。 で、戦場のメリークリスマスが収録されている、このCDを購入したのですが、なかなかにメロディックないい曲ぞろいなんですよ。1曲目の「Fantasy!」は、オープン・チューニングの曲で、あの名曲「サンバースト」を彷彿とさせるような、躍動感にあふれた佳曲です。他にもオリジナル曲に聴き応えのある、よい曲がそろっています。それから、本来チターで奏でられる「第三の男のテーマ」を、ギター演奏で、まるでチターの調べを聴いているようなノスタルジックな雰囲気を味あわせてくれるのが素晴らしいですね。ふつう、歌の入らないギターのソロアルバムは単調なんで、聴いていて途中で飽きてしまうのですが、このCDはそんなことないです。 (2003年02月14日 記) 押尾コータローは1968年、大阪生まれの大阪育ち。「ゴンチチ」のゴンザレス三上、チチ松村も大阪だし、アコースティック・ギター奏者で有名な人は何故か大阪の人が多い。それには理由があって、大阪には日本のフォークギター奏者の最高峰、中川イサト氏がいたからです(たぶん)。実際、押尾コータローは「中川イサト・ギター教室」の生徒さんでした。 ぼくは高校生のときフォーク・ギター部に所属していて、25,000円のモーリス・フォークギターの中古品を 10,000円で買ってきて、日夜練習に励んでいました。当時ラジオCMで、谷村新司さんが「モーリス持てば、スーパースターも夢じゃない!」って、言ってましたからねぇ。スリー・フィンガー奏法がようやく弾けるようになった頃、加川良 のコンサ−トでサイドギターを弾いていた中川イサトに出会いました。カッコよかった。すっごく。 さっそく伊那の「平安堂レコード」で購入したのが『お茶の時間』中川イサト(CBS/SONY/CSCL 1253) でした。このレコード、何度も何度も聴きましたねぇ。今でもCDでよく聴きます。個人的名盤ベスト10に入るレコードです。2つ折りのジャケットを開くと、漫画雑誌ガロに登場するような街のイラストと、手書きの歌詞が載っていて、あまり大阪っぽくない都会の寂しく静かな彼の音楽と妙にマッチしているのでした。しばらくして「中川イサト・タブ譜付き楽譜集」が発売されたので、ぼくは驚喜して、毎晩楽譜とにらめっこしながら彼のギター・テクニックの拾得すべく必死で練習しましたよ。「その気になれば」とか「かすていらのかをり」とか。(もう少し続く予定) (2003年02月16日 追記) |
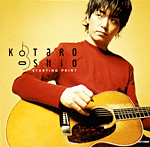 押尾コータロー (東芝EMI/TOCT-24820) 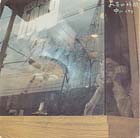 中川イサト (CBS/SONY/CSCL 1253) 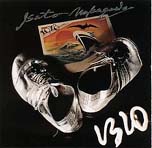 中川イサト (CBS/SONY/SRCL-2048) 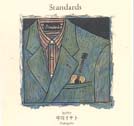 中川イサト Seals Records (SEAL-016) |
イズラエル・カマカヴィヴォオレ『Facing Future』(レイ・レコード/LEIR0046)\2800(税込) ---------------------------------------------------- ■癒しのハワイアン イズラエル・カマカヴィヴォオレ■ ---------------------------------------------------- ●最近テレビCMでやたらと耳にする曲があります。"Somewhere Over The Rainbow Way up high" 元ちとせがこぶしを効かせて歌う『虹の彼方に』 を初めて聞いた時は、ほんとビックリしました。ミスマッチの妙とでも言いましょうか、変に耳について困りました。少なくとも山崎まさよし・ヴァージョンよりはずっとよかった。 起死回生を狙う三菱自動車「コルト」のCMだったのですが、詳しくは<こちら>をご覧ください。 でも、ぼくが思うに「この曲」の最も優れた歌い手は、何と言ってもイズラエル・カマカヴィヴォオレです。この舌を噛みそうな名前の主はモダン・ハワイアン・シンガーの代表的な歌手として、地元ハワイでは大変な人気歌手だった人です。 日本でも数年前に「アケボノ〜 ムサシマル & コニシキ〜」というへんな日本語の相撲取りの歌『天国から雷』がラジオでヒットしたこともあります。その彼が歌う『虹の彼方に』 は 『Facing Future』(1993)に収録されています。小錦よりも体重があったと言われる巨漢のイズラエルがウクレレ一本で、この曲をじつに軽やかに歌うのですが、とにかくこれが素晴らしい! ネット上でも一部聴けます。原曲を独自にアレンジしてあって、マイナー・コードが多用されているので、ちょっと寂しい曲調になっています。また、なぜか曲の途中からサッチモの「What A Wonderful World」に変わって、最後にまた「Over The Rainbow」にもどって終わります。 ●あの『ER』第8シーズンの最終回が、アメリカでは2002年5月9日に放映されたのですが、その回のBGMが、このイズラエルが歌う『虹の彼方に』だったのだそうです。日本ではまだ未公開ですが(^^;) この回はハワイが舞台で、グリーン先生が登場する最後の回になりました。アメリカでは、この『ER』放映後の1週間で、何と49,000枚もイズラエルのCDが売れたんですって。 イズラエルが歌う『虹の彼方に』の別ヴァージョンが、『モナリザ・Alone in Iz World』 でも聴けます。イズは、38歳の若さでこの世を去りました。ハワイでは国葬級の扱いだったそうです。 (2003年01月09日 記) |
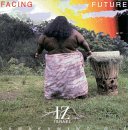 (レイ・レコード/LEIR0046) 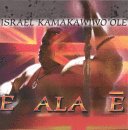 (レイ・レコード/LEIR0018) 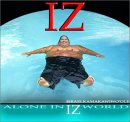 (レイ・レコード/LEIR0061) |
エリス・レジーナ(ユニバーサル / UICY-3508)\2141(税込) ---------------------------------------------------- ■ブラジルの歌姫 エリス・レジーナ■ ---------------------------------------------------- ●ジャズにしても、キューバ音楽やブラジルのサンバにしても、みな白人の西洋音楽に黒人のリズム・ビート感が融合してできた混血音楽です。ジャズはポピュラー音楽の主役の座を脱落して、もうずいぶん経ちますが、キューバ音楽やブラジル音楽は世界の大衆音楽の最前線でつねにガンバってきました。特に90年代イギリスのクラブシーンや、橋本徹さん選曲のカフェ・ミュージックでは、ボサノバブーム以降の1960年代末〜70年代初めのブラジリアン・ミュージックが好んで取り上げられ、その古くささをぜんぜん感じさせない新鮮な響きに、みなが驚きました。 中でも注目を集めたのが、エリス・レジーナです。ボサノバの女性ヴォーカルと言えば、ナラ・レオンとかアストラット・ジルベルト、最近では小野リサみたいに「ごにょごにょ、ぼそぼそ」と歌うものだと思っていたら、エリス・レジーナはぜんぜん違うんですね、これが。 どこかのウェブサイトで誰かがこう書いていました。「エリス・レジーナはブラジルの水前寺清子である」と。いやぁ、じつにうまいことを言うもんです。パンチの効いた元気のいい張りのある歌声で、抜群のリズム感でもってアップテンポの曲をぐいぐいと のりのりで歌いまくるのですから。 そんな彼女の魅力が全開したCDが、この『エリス・レジーナ イン・ロンドン』なのです。1曲目の「帆掛け船の疾走 」を聴いてみて下さい。エリスはその抜群の歌唱力でもって聞き手の心をいとも簡単に鷲づかみにします。何かこう「わたし、歌うのが楽しくって楽しくって仕方ないのよ!」っていう雰囲気がじんじん伝わってきて、特に曲の途中でヴォーカルと微妙にズレていったリズム陣が反転して裏のりになる場面が、何度聴いてもじつに気持ちいいのです。そして3曲目の「シ・ヴォセ・ペンサ 」のサビの部分を熱唱するエリスのカッコイイことといったら。そりゃあもう凄いですゼ、旦那(^^;) このレコードは、1969年にエリスがヨーロッパ巡業中のロンドンで、たった2日間で12曲を一気に録音したものだそうです。エリスのブラジル勢のバンドとイギリスの46人のオーケストラはこの時初対面だったそうですが、なんと信じられないことに、すべて一発同時録音のうちにロンドンのスタジオで完成されたんですって。奇跡に近い話ですよね。 『エリス・レジーナ イン・ロンドン』が、「動 の エリス 」の代表作であるとするなら、『エリス & トム』は「静 の エリス 」の代表作で、この2枚は表裏一体となった名盤です。特に1曲目の「三月の雨 」におけるアントニオ・カルロス・ジョビンとのデュオの心地よさといったら、もう、この世のものとは思われません。スローなバラードでもじっくり聴かせる確かな表現力があるから、エリス・レジーナが「ホンモノ 」であると、再評価が高まっているのでしょうね。 前述の橋本徹氏選曲によるエリス・レジーナのベスト盤 が『ELIS REGINA for Cafe Apres-midi』として出ていて、前半にはシングル盤でしか出ていなかったレアな音源 が集められていて(例えば、サッカーの神様ペレとのデュオとか)マニアを喜ばせてくれます。代表曲を含む28曲を一気に聴くことができて、お得な一枚です。 エリス・レジーナは、1982年に36歳の若さでこの世を去ります。ブラジル天才女性歌手の早すぎる死は、アルコールと薬物中毒によるものでした。 (2002年12月08日 記) |
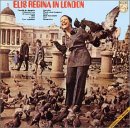 (ユニバーサル/UICY-3508) 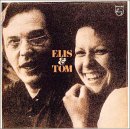 (ユニバーサル/UICY-3507) 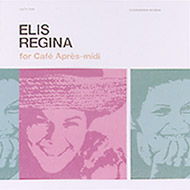 (ユニバーサル/UICY-1106) |
■森山さんのこと■ 『ハッシャバイ』森山威男カルテット ---------------------------------------------------- ●このページは、ぼくが好きなCDを「勝手に」紹介するコーナーなのですが、中でもこの曲は、もう「めちゃくちゃ」好きなんです。たぶん、日本人ジャズのレコードの中では、最も数多くターンテーブルにのっかって、繰り返し繰り返し、何度も何度も聴いたレコードだと思います。 このCD、ほんと「名曲」ぞろいなのです。1曲目「SUNRISE」の、めくるめくスピード感、3曲目「NORTH WIND」の物憂いけだるさ。この曲は、映画『十九歳の地図』柳町光男監督作品の中で、主人公とゲスト出演のフォーク歌手「友部正人」が、競争しながら高層アパートの新聞配りを繰り広げるシーンで使われていました。 そして、2曲目に入っているのが、哀愁の名曲「ハッシャバイ」。テナーサックスでソロを取るのは、当時の森山威男4で「日の丸突撃隊」の異名をとった小田切一巳! 彼は、このレコーディングの数年のち、敗血病のためにまだ若き命を悪魔に奪われてしまいます。ほんとうに惜しい、未完の大器でありました。コルトレーンと言うより、ハンク・モブレイみたいな「もこもこ」した感じのテナーサックスを吹く人で、細身の体に似合わない図太い音で、哀切 なメロディが次々と溢れ出す彼のこのソロプレイは、何度聴いてもため息が出てしまいます。 サックスに続いてソロを取るのが、ピアノの板橋文夫。このピアノソロが、これまた「絶品!」なのです。音数は多いのだけれど、無駄な音符はいっさいありません。ジャズに限らず、これほどまでに聴き手の心を打ち振るわすことができるピアニストを、ぼくは板橋さんの他には知りません。とにかく泣けます! 涙がちょちょぎれます! 「ハッシャバイ」を演奏する人はけっこう珍しくて、本場アメリカのJazz men でこの曲を得意としているのは、テナー・サックス奏者のジョニー・グリフィンだけです。コペンハーゲンにあるジャズ・ライブハウス「カフェ・モンマルトル」でのライブで、ケニー・ドリュー・トリオをバックに演奏された「ハッシャバイ」もいいですが、『The Kerry Dancers』(ビクターエンタテインメント - ASIN: B00004SYJH)に収録されている「この曲」のほうが、ぼくは好きです。 森山威男4の、このレコードが録音されたのは、1978年2月27日。当時ぼくは勉強もせずに、筑波のジャズ喫茶『AKU AKU』に入り浸っておりました。マスターの野口さんは、赤字覚悟で月に一度は東京から有名ミュージシャンを呼んでは「ライブ」を行っていました。音楽だけでなく、演劇人も「筑波」に呼ばれて来ていましたね。ぼくが観たのは大田省吾さん主宰『転形劇場』の芝居「小町風伝」。(主演は、今をときめく 大杉漣! でしたよ。) そんな中に、「森山威男カルテット」はいて、ぼくは『AKU AKU』で初めて彼らのライブを体験し、圧倒されてしまい、その後、新宿「ピットイン」や西荻窪「アケタの店」で、森山威男カルテットのライブがあると聞けば、迷わず駆けつけて聴いてきました。とにかく、当時の「森山威男カルテット」は本当にめちゃくちゃカッコよかった! 今でも覚えているのは、とある筑波「アクアク」での昼下がり。午後いちでリハーサル現場に現れた板橋文夫さんが、おもむろに「アクアク」のグランドピアノの前に座り、指を鍵盤の上に載せたのです。続いて流れてきたのは、森山カルテット で以後ずっと演奏が続けられることとなる、もう一つの名曲「ワタラセ(渡良瀬)」のフレーズでした。ピアノのサイドで、それを聴いていた小田切さんは「いい曲だね、キーは何?」と言いながら、ソプラノサックスでピアノの音の後に続いたのでした。板橋さんは「この間作った曲なんだけど、どう?」確か、そう言いました。 ぼくは「かの名曲」の誕生の瞬間に、立ち会えたことを、誇りに思っています(^^;) 小田切一巳さん亡きあと、森山威男4のテナーサックス奏者に就任したのは、国安良夫さんでした。直木賞作家の胡桃沢耕史さんの愛娘、ピアニストの清水くるみさんの夫でもあった国安良夫さんは、笑顔のとても素敵な人でしたが、交通事故のために、その1年後、短い人生を閉じます。 (森山威男カルテットのことになると、思い入れが強すぎちゃって、話が終わりそうにありません) ●森山威男といえば、山下洋輔トリオの初代ドラマーとして世界を股にかけて活躍してきた、伝説の名ドラマーです。当時のLP、CD「CONCERT IN NEW JAZZ」「CLAY」「FROZEN DAYS」「UP-TO-DATE」「CHIASMA」は、ぼくも持ってはいるのですが、残念なことに、森山さんがいた「山下洋輔トリオ」を「on Time」で聴いたことがないのです。ぼくが現在進行形で追っかけることができたのは小田切一巳さん〜国安良夫さんが在籍した当時の「森山威男カルテット」だったので、どうしても「その頃」のレコードが今でも一番印象に残っているのです。 その後、森山4からピアノの板橋文夫さんが辞めて、2テナー(井上淑彦・榎本秀一 or 藤原幹典)のピアノレス・カルテットでしばらく演奏を続けた森山さんは、1986年の夏「ふつうのオジサンに戻りたい!」と、突如宣言してドラムのスティックも捨て、奥さんの実家に近い岐阜県多治見市で「珈琲店のマスター」に変身してしまったのです。しかし、不世出の名ドラマーの引退を惜しむ声は全国に拡がり、復活を請われて、地元で年に1〜2度ライヴが行われました。 その貴重な記録が、1990年12月28,29日に、名古屋のライヴハウス「Lovely」で録音された『Live at Lovely』(ディスクユニオン- ASIN: B00006AFXF)なのです。井上淑彦(ts)、板橋文夫(p)、望月英明(b)、森山威男(drs) という史上最強のメンバーで、しかも、板橋さんとは「じつに久しぶり」のセッションでもあって、とにかく最初から全員が全速力で突っ走る「ものすごい」CDです。 その後も、森山さんは「あくまで楽しみのために」時々、たまーに人前でドラムをたたく、というスタンスを現在まで変えることなく続けてきました。 大学を卒業して地元の信州に帰ったぼくは十数年間、森山威男カルテットのライヴから遠ざかっていたのですが、富士見高原病院の小児科一人医長をしていた時、八ヶ岳の麓にある「富士見高原スキー場」で1996年の夏の終わりに『ジャズ・フェスティバル』が開かれ、快晴の高原の下でぼくは、森山さんと15年ぶりの再会を果たしたのです(もちろん、一方通行ですが(^^;)この時の「ジャズ・フェス」に南博トリオのゲスト・ボーカルとして出演していたのが、まだメジャーになる前の「綾戸智絵」 で、この「異様にあっかるい、大阪弁でまくしたてるオバハン」に、ぼくは圧倒されたのですが、介護班のテントの中で、もっとビックリしている人がいました。それは、日本ジャズ界の影の功労者、岡崎市で外科医院を営む「内田修先生」です。 内田先生は すかさず、ステージの終わった綾戸に駆け寄り「ぼくが紹介するから、メジャーデビューしようよ!」そう言って、レコーディング・メンバーの設定からレコード会社の選択まで全て請け負って、綾戸智絵のCDは製作されたのでした。 話が横道にそれてしまいました(^^; 不思議なことに、森山さんにも人知れず彼のことをサポートする「ドクター」が、地元の岐阜県土岐郡笠原町にいたのです。その先生は、「藤井医院」藤井修照先生で、森山さんに惚れ込んでしまった先生は、とうとう自宅横に「スタジオ」を建設、以降、森山さんのために数々のレコーディングを行い、自主レーベルでCDまで製作してしまったのでした。 その、「Fレーベル」最新作が、森山威男『森』『山』 の2枚なのです。『森』は自主レーベルには大変珍しく「スイングジャーナル選定ゴールドディスク」に選定されるという快挙をうち立てました! (もう少しつづく) ●で、その「新生・森山カルテット」の話になるのですが、これがまた、じつにいいユニットなのです。ピアノの田中信正さんは、板橋さんとは全然違うタッチなんだけど、森山さんとの相性は抜群! おでこをピアノの鍵盤にこすりつけそうなぐらい前屈みになってピアノを弾く姿は、まるでビル・エバンズみたい、とのことです(ぼくはまだライヴを見てないので知らないのですが) そしてフロントでテナー・サックスを吹くのは音川英二 。新作『森』の3曲目に入っている「In A Sentimental Mood」を聴いてみて下さい。サックスの最初の音を聞いてぼくは「あっ! 小田切一巳が帰ってきた!」そう錯覚してしまいました。あれは20年前の西荻窪「アケタの店」、黄昏時の店先にはいつも、人待ち顔の森山さんが白のスーツをビシッと決めて(まるで○○組の若頭みたいな雰囲気で)立っていました。 当時のサックスは小田切一巳さんで、ライヴが始まって2曲目はきまって「In A Sentimental Mood」だったのです。テナーがテーマを奏でると、バックで森山さんがドラムのスティックをブラシに持ち替え、スタタタタタッ、どっしゃーん、と太鼓を叩くのですが、ここがメチャクチャ気持ちいいんです。 新しいCDでも、まったく同じ アレンジ。泣けてきましたよ。 新生・森山カルテットの画像は、 こちらで 見ることができます。 (2002年 12月06日 追記) |
 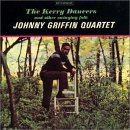 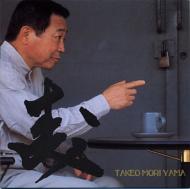 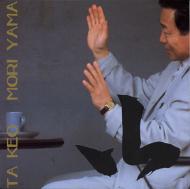 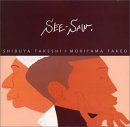 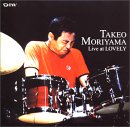 |
----------------------------------------------- ■牧師さんが唄うR&B■ 『People』小坂忠 (EPIC RECORDS/ESCL2267) ----------------------------------------------- http://www.hmv.co.jp/Product/Detail.asp?sku=975015 ●日曜日の朝、車に乗って、FMラジオをつけると、流れてきたのがこの曲、『夢を聞かせて』。アコースティック・ギターの印象的なイントロに続いて「いぶし銀」のヴォーカルが被さる。えもいわれぬ心地よさと懐かしさ。そう、帰って来たんだ、日本のジェイムス・テイラー、あの伝説の「小坂忠」が!! 曲がセカンド・フレーズに入る直前、絶妙のタイミングでベースが加わるのだけれど、このベースを弾くのはもちろん「細野晴臣」。いいなぁしみじみいい。 ぼくが小坂忠に初めて出会ったのは『ほうろう』というタイトルのLPで、 http://www.hmv.co.jp/Product/Detail.asp?sku=49279 まだ多感な高校生だった頃のこと。「はっぴいえんど」を解散した細野晴臣が鈴木茂・林立夫・松任谷正隆・矢野誠・山下達郎・矢野顕子・吉田美奈子・大貫妙子らと結成した「ティン・パン・アレー」でプロデュースしたこのレコードは、とにかくめちゃくちゃカッコよかった。お気に入りはB面1曲目に入っていた「しらけちまうぜ」で、当時、スキー場でよくかかってましたっけ。 この『ほうろう』は名盤の誉れ高いレコードなんですが、この後、小坂忠は何故か日本のポップ・シーンから突然、消えていなくなってしまうのです。 ●その日曜日の朝のラジオ番組は『南こうせつ・週末はログハウスで』だったのだけれど、その日ゲスト出演していたのが、26年ぶりでメジャー・レーベルからCDを発売したばかりの「小坂忠」だったんです。その中で、南こうせつが「忠さんは牧師さんだから……」と言っていたのを耳にして「えっ?」って思ったんですね。 で、インターネットで検索してみたら、こんなサイトが見つかりました。 http://www.daisyworld.co.jp/creatures/cekosaka05.html 『ほうろう』でミュージシャンとしてピークにいたはずの小坂忠は、当時、人間個人としてはボトムにあったようです。音楽面でも人間関係でも行き詰まっていたことに加えて、1歳10ヵ月の1人娘が熱湯を被って大火傷して。 偶然足を踏み入れた教会で、そこの人たちが一緒に祈ってくれた。(中略)信仰などには一切興味のなかった彼が、それを機に教会に足を運ぶようになった。クリスチャンになり、牧師になった。教会音楽にも触れ、「この中で、ぼくができることはなにかないか」という思いが募る。そこで、ゴスペル専門のレーベルを立ち上げ、ふたたび歌いはじめる。 実際、むかしの小坂忠のレコードジャケットの写真とか見ると、山猫みたいに眼光鋭く、ちょっと近寄りがたいような印象があるのだけれど、今の忠さんの表情はぜんぜん違って、なんともあったかく、包容力がにじみ出ているのです。 小坂忠は、1991年から日本フォースクエア福音教団秋津教会(所沢市)の正式な牧師さんで、日本のコンテンポラリー・クリスチャン・ミュージックやゴスペル・ミュージックの中心人物として、ぼくらのぜんぜん知らないところで、地道に活動を続けていたのでした。 (もう少し続く) http://www.hat.hi-ho.ne.jp/~fsq-akitsu/about.html クリスチャンの布教活動の一環として、コンサートを続けている人として有名なゴスペル・シンガーに「レーナ・マリア」というスウェーデン生まれの女性歌手がいます。重度のハンディキャッパーながら、感動的な歌声を聴かせてくれることから、久米宏の「ニュース・ステーション」や、「徹子の部屋」で10年以上も前から取り上げられていたり、長野パラリンピックの開会式で歌ったりしているので、ご存知の方も多いかと存じます。数日前も、「日本テレビ」夜23時からのニュースの特集で、この秋の彼女の日本コンサート・ツアーの様子が取り上げられていました。 http://www.lena-japan.com/ このコンサート・ツアーで彼女は、10月30日に長野県では1ヵ所だけ、伊那市に来ていて、伊那文化会館でコンサートを開いています。ぼくは女房と子どもを2人連れて聴きに行ったのですが、それはそれは素晴らしいコンサートでした。いまどき全席自由で、チケット代は1人たったの3000円!。外タレなのにですよ! 彼女の歌声は本当にスバラシイです。そのことは、彼女の両手が生まれながらに無いことや、彼女の左足が膝上から存在しないこととは、まったく関係はないと、ぼくは思いたいのです。そういう「もろもろ」の先入観なしで、彼女の歌声は、十分に感動的だ! 目を瞑っていても、ココロの奥底まで響いてくる歌声。本物の歌声! そこには、たしかに、ぼくには理解の及ばない、深い信仰があるのです。それが別にクリスチャンではない「ぼく」のココロにも振動して来るのです。いったい、この感動は何なんだろう? 障害があることとは全然違った次元から来る問いかけ……。 この「ヒューマン・ヴォイス」に秘められた「パワー」に関しては、充分に論考する必要がありますので、この続きは、また次回とさせていただきます(^^;) (2001年 12月23日 記) | 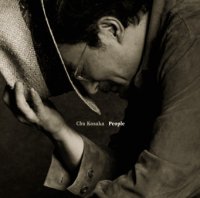 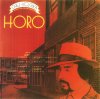 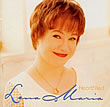 |
●綾戸智絵の新譜が、なかなか良いですぞ!● http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00005QCC6/qid=1004566155/sr=1-2/re f=sr_1_0_2/250-7666493-6504235 相変わらず、綾戸の「追っかけ」を続けているんですが、年に2〜3枚も次々と新しいCDが発売されるペースには、さすがのファンとしても息切れがして、ついて行けなくなりまして、最近は「TSUTAYA」でレンタルCDを借りてきてはパソコンにコピーしてお茶を濁していたのです、じつは(^^;) で、また出たんです。綾戸智絵のCD。「うへっ」って、げっぷが出そうになるのを堪えて聴いてみたら、これが何と、素晴らしい出来なんですよ!! 前回のCDは、弾き語りライヴ「2枚組」で、「アヤド」の魅力はソロの弾き語りにこそある、と思っていただけに予想通りの仕上がりでした。でも、それ以上のものはなかった。何だかちょっと不満でした。 それが、今度のCDでは「原信夫とシャープス&フラッツ」という国内最高峰のビッグバンドを従えて、唄いまくるんです。いや〜、たまげました。しばらく前に、NHKBS2で放送された「山下洋輔&綾戸智絵」のライヴを見た時にも感じたんですが、アヤドは、あの世界の「ヤマシタ」を「屁」とも思っていないんですね。畏怖とか尊厳とか、そういった感情が一切ない。山下さんを「単なるバック・ミュージシャン」、主役は「ワタシ」としか見ていないんです。 それは今回のCDでもおんなじで、「原信夫とシャープス&フラッツ」と言えば、アメリカではデューク・エリントン・オーケストラか、カウント・ベイシー・ビッグ・バンドに相当するような、老舗の名ビッグ・バンドなのに、何と綾戸は、「サシ」で渡り合おうとしてるんです。身分相応もなく。だから、だいぶ背伸びしてるのが「見え見え」なんですが、まるで、お釈迦様の掌で悪戦苦闘している孫悟空みたいで、微笑ましいんですね。 綾戸が、老舗のJAZZ月刊誌『スウィング・ジャーナル』から、ず〜っと一切無視され続けていることや、一部のジャズ関係者から毛嫌いされている原因は、たぶんこのあたりにあるんじゃないかなぁ。芸能界では新人のくせに、生意気すぎるんですよ。 でも、このCDのデキはいい! キーワードは「美空ひばり」。4曲目に入っている『恋人よ我に帰れ』は、何とかつて数十年前に「原信夫とシャープス&フラッツ」が美空ひばりと共演したレコードと、まったく同じアレンジで演奏されるのです。ちなみに、オリジナルはこのCDで聴けます。 http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00005EL9L/qid=1004566007/sr=1-205/ ref=sr_1_0_205/250-7666493-6504235 この美空ひばりのCDは名盤で、ぼくも持っています。 驚くのはラストに入っている「サマータイム」。 アレンジ(前田憲男)が、あの懐かしい『真っ赤な太陽』の雰囲気なんです。 http://www.fsinet.or.jp/~juice/Slit-j/HibariMisora.htm 美空ひばりがブルー・コメッツと共演して大ヒットした「この曲」の作曲者が、じつは「原信夫」だったのです。ズズチチャ、ズズチャチャ、というモンキーダンスのリズム、美空ひばりの、ちょいと不似合いなミニスカート。懐かしいなぁ。 CDは「A列車で行こう!」で終わるのですが、じつはコンサートのアンコールで唄われた曲が、何と!『真っ赤な太陽』。 来月発売される予定のDVDには収録されるそうです。楽しみだな(^^) (2001年11月12日 記) |
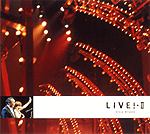  |
北原こどもクリニック