ファラオ・サンダース、それから、吉本隆明『ひきこもれ』 2003/10/31
●最近は、あまり熱心にジャズを聴かなくなっちゃったんですが、学生の頃はジャズばかり聴いていました。お気に入りは、森山威男カルテットと、アート・ペッパー(as)、それからファラオ・サンダース(ts)。
小児科研修医になって、松本で過ごした頃、緑町の「凡蔵」の左隣に、「アミ」っていうジャズ喫茶がありました。今はたしか火事で焼けちゃってないのだけれど、やる気があるんだかないんだか、のほほんとしたマスターが一人でいて、お客はめったにいない不思議な空間でした。
無口なマスターで、ほとんど話をしたことがなかったのだけれど、ぼくが「ファラオ・サンダースが大好きなんです」って言ったら、黙ってレコード棚からインパルス時代の傑作『Elevation』と『Love In Us All』の2枚のLPを取り出してきて、見せてくれました。そうして『Love In Us All』A面「 Love is Everywhere 」をターンテーブルにのっけて彼は、ぼそっと一言。「ファラオなら、こいつが最高だな。」
「よかったら持ってきなよ。貸してやるよ」って、マスターはその2枚のLPをぼくに貸してくれました。うれしかったなぁ。あの時録音したカセットテープ、たしか取って置いたはずだけど……
そのインパルス・レーベルの2枚も、今月CDで国内発売されました。今月発売された音楽雑誌「レコード・コレクターズ」11月号、「ジャズライフ」11月号、「スイングジャーナル」11月号では、こぞってファラオ・サンダースの特集記事(扱いは小さいですが)を載せました。なんだか感慨深いです。20年以上たって、ようやく時代がファラオに追いついたのだから。
http://www.so-net.ne.jp/e-novels/yomimono/aiueo/fu.html
こことか読むと、ぼく以外にも、けっこう熱烈なファラオ・サンダース・ファンがいることがわかって、苦笑してしまいます。それにしても、この田中啓文さんの文章はうまいなぁ。そうなんですよ、結局は「はったりの人」なんだな、ファラオって(^^;)
●『ひきこもれ』吉本隆明 大和書房(2002/12/10) \1400 読了。
面白かったです。そのとおりだよなぁ。この人、じつに真っ当なこと言ってるよ。
石焼きいも リベンジ 2003/10/29
●昨日は、次男の幼稚園のイモ掘り大会で、彼は「大きな大きなおいも」を1個持って帰ってきました。天ぷらにする? って訊いたら、どうしても石焼きいもがいい、と言い張るので、午後の外来が終わったあと綿半ホームセンターへ「玉砂利」を買いに行ってきました。
玉砂利は園芸用の大袋でしか売ってなくて、そんなに必要ないのだけれど仕方ありません(^^;) 水洗いしたあと、炭火おこし用のファイアー・スターターで、あらかじめ玉砂利を加熱しておき、プレヒートしたダッチ・オーヴンに敷きつめ、お芋を入れてから、さらに玉砂利を上から被せました。大きな大きなおいもでも、12インチのオーヴンなら大丈夫。
■ふたをして、弱火で1時間で出来上がり。今回は成功です! 蓋を取ると、プーンと、あの香ばしい石焼きイモのにおい。お芋はホクホク、下面が適度に焦げて、まさに石焼きいも屋さんの「あの」おいもの味です。この焦げたイモの皮がまた美味いんだな、これが(^^)

読み聞かせサポーター養成講座(入門) 2003/10/26
●このところ、日曜日は忙しくて、女房・子どもほったらかしで出歩いているので、家族からはすこぶる評判の悪い父親でした(^^;)
先週は「不登校・引きこもり」の勉強をしてきましたが、今週は、朝 8:18 伊那市駅発の飯田線に乗って、松本まで出かけました。松本市立図書館・視聴覚室で開催された「読み聞かせサポーター養成講座(入門)」に出席するためです。
絵本に関する講座は、各地の図書館を中心にいろんな場所で開かれているのですが、たいてい月曜日の午前中とか、もしくは土曜日の正午からとなっています。うちは土曜日の外来を、午後2時までやっているので、まず絶対にこうした講座には出席できません。ところが、今回の講座は日曜日開催だったので、めったにないチャンスとばかり、応募したのでした(^^)
■講師の先生は、茅野市図書館長:牛山圭吾先生、そして、牛山先生の奥さんであり、茅野市の読み聞かせグループ「おはなしくれよん」の代表を務める、牛山貞世さん。そうして、松本市沢村で「ちいさなおうち」という児童書専門店を営み、JPIC 読書アドバイザー講師としても有名な越高一夫さん。
当日参加した人は100人近くいましたよ。でもね、男性はぼくを含めて二人きり。あとの98人は女性。何だかぼくは、ものすごく場違いな所に来てしまったなぁ、と後悔いたしました(^^;; だって、まるで、シャボン玉ホリデーの「お呼びでない」植木等状態だったのですから(^^;)
▼そうは言っても、今回参加できて、ぼくはとっても勉強になりました。大人だって、読み聞かせしてもらうと、ものすごく気持ちいいことが再確認できたからです。それから、他人の読み聞かせの仕方を注意深く観察することで、そのノウハウを盗み取ることができたのです。これは、本を読んだだけでは決して解らない、実体験の勝利でしょう。
越高さんの語り口の上手さは体験ずみでしたが、今回一番の収穫は、牛山貞世さんを発見したことです。この人はスゴイ!。ほんとうに絵本のことがよく分かっている、数少ない大人の人なのです。そういうことが、よーく分かった。今度、もっとじっくりと、彼女のお話を聴いてみたいな(^^)
●それにしても、男性の参加者がこうも少ないのか? 不思議に思って、終了後に牛山先生に訊いてみたんです。そしたら「今回の講座はボランティアで保育園や小学校に読み聞かせに行く人たちのためのものだから、平日ボランティアで読み聞かせするお父さんはなかなかいませんよね。でもこれからですね。紙芝居をやってみたいお父さんはけっこういるし、茅野市では、父親向けの絵本講座の要望もあります。」とのことでした。
そうかそうか、ボランティアの読み聞かせね。いや、ぼくだって11月には、高遠第一保育園と伊那市竜東保育所で、秋の内科健診のあと、例によって絵本を読んでくる予定ですので、参加して間違ってはいなかったな、きっと(^^;)
『もっとコロッケな日本語を』東海林さだお(文藝春秋) 2003/10/24
●前回、ちょっと愚痴っぽく書いてしまったら、励ましのお便りが2通届きました。Sさん、Kさん、メールどうもありがとうございました(^^)
大丈夫です、2年目もぼちぼち更新を続けてゆきます。
●ここの日記の、2003年1月25日に、「ドーダの人々」に関して書きましたが、この回を収録した「男の分別学」の単行本が、この6月に既に発売されていました。タイトルは『もっとコロッケな日本語を』東海林さだお(文藝春秋)\1095(税別)2003/06/15 初版。
「ドーダの人々」は見事「巻頭」を飾っていましたよ(^^;) 「信州蕎麦打ち行」では、長野県富士見町乙事の「おっこと亭」が出てきて、うれしくなってしまいました。鼻の穴で蕎麦粉が固まって、ゆらゆらしていたオバチャンて、もしかして、あの人かなぁ(^^) ところで、『もののけ姫』に登場する、森繁久弥が吹き替えした、あの「おっことぬし」って、富士見町乙事から採られたんですって。宮崎駿さんの別荘が富士見町にあるから「おっこと」の地名が使われたのです。
この本で一番面白い所は、漫画家の高橋春男さんに東海林さんがエッセイの書き方の極意を伝授している対談です。以下、東海林さんのお言葉で、特に印象的だったものを、引用させていただきます。
やっぱり文章もね。
とにかくパターン化しちゃうとダメですよ。常に壊していかないと続かない、何十年も。
向田邦子さんのエッセイというのはパターンがあるんですよね。さり気なくあるテーマで始まって、いつの間にか話は違うほうに行っちゃうの。だから、
ああ、こっちの話なんだあって思ってると、一番おしまいで最初の話に戻って繋がるんです。そうすると、読者は非常に快感を憶える
いい文章を目指す。
ほら、いい日本酒はスラスラ飲めるでしょう。とりあえずスラスラ読めるっていうのは大事なんですよ。
やっぱり文章ってリズム、呼吸なんだよね。『声に出して読みたい日本語』っていう本がでたでしょ。声に出して読むと、人間の呼吸の生理と一致してない文章はつっかえちゃうんだよね。
高橋 :ああ、だからかな。僕、東海林さんの雑文読んでて、これ落語家が喋ったら、そのまま落語になるんじゃないかという感じがしましたよ。
でも、結局は東海林さんの人格が出るんだと思うんですよね。あんまり詰め込まないで、あっさり行こうみたいな。
東海林:うーん、お肉屋さんのコロッケみたいな文章を書きたいと思ったことはあるね。
高橋 :ジャガイモばっかりの。
東海林:中に挽き肉の一粒でも入ってると嬉しい(笑)。
『もっとコロッケな日本語を』東海林さだお(文藝春秋)(p134〜142)より引用。
ホームページ立ち上げ「一周年」 2003/10/22
●今日、10月22日で、ホームページ立ち上げ満1周年を迎えました(^^) ウレシイです。糸井重里さんは言いました。自分のサイトの運営は、誰でも一年間はちゃんとやる。でも必ず「2年目の壁」がやってくる。多くの人が、この壁にぶち当たって、サイトの更新作業への熱意と情熱を消失し、ほったらかし状態となり、後には無惨にも野ざらしにされた住人のない廃墟が、インターネット上に放置されるのだ、と。
ぼくがこのサイバースペースに自分の痕跡を残す理由は、ただひとつです。ぼくがもし、明日突然死んでしまったとしたら、妻と二人の子ども、それから兄たち、そして母親だけは、少なくとも彼ら彼女らが生きている間は、ぼくのことを憶えておいてくれているかもしれない。でも、それだけ。それだけでも贅沢なのかもしれないけれど、でも、ぼくはさびしい。
●むかし読んだSF小説に『太陽風交点』堀晃(徳間文庫)というのがあって、ぼくはこの「SF短編小説集」が大好きなのです。とある惑星に主人公が降り立った時には、その惑星のかつての住人が隆盛を際めた時代を、既に数億年が過ぎ去っているのです。でも、確かに、かつての住人の息吹を、小説の主人公は感じるのです。悠久の時を超えて……
そういう感覚って、もしかしたらネット上においてなら可能かもしれない、そう思っているのです。だから、今夜も夜更かしして、いったい誰が好きこのんで読むかもわからない文章を、つれづれなるままに書き連ねているのでありましょう(^^;;
堂々と豊に、引きこもれ! 2003/10/21
●10月19日(日)に、伊那合同庁舎で「不登校の理解と支援のあり方」というフォーラムが開かれました。主催は子どもサポートプラン上伊那地域ネットワークフォーラム実行委員会です。この委員会は、不登校の子どもとその家族をサポートするために、県主導で長野県下7地域に、行政・学校・民間で横の連携を取りながら支援活動を行うための中核として、本年度から出来上がった組織なのだそうです。活動資金は、今年は県から予算がついているそうです。
ぼくも勉強しに、このフォーラムに行ってきました。まずショックだったことは、引きこもり当事者の体験談でした。20代前半の男性、女性一人ずつが壇上に上がって、自らの赤裸々な不登校・引きこもり体験を語ってくれたのです。しかも「それ」は、決して過去の物語なのではなく、現在進行形でもあるのです。一言で引きこもりと言っても、それぞれ事情はまったく異なります。ただ、その直接の引き金が、クラスメート・担任の先生も含めた「いじめ」であったことは共通していました。
●続いて、岐阜大学医学部精神科助教授・高岡健先生の講演がありました。この先生のお話がこれまたビックリするような内容で、たまげてしまいました。曰く、今の世の中、子どもが「引きこもり」にならないほうがむしろ異常なんじゃないか? 引きこもりを経験しない人生なんて、なんと薄っぺらい、つまらない人生なのでしょう。引きこもっている期間は、自分を客観的に見つめ、世間を見つめ、生きて行く上で、結局最後はひとりが強いんだと確信を得るためにも、どうしても必要なライフ・ステージなのだと。
成人してからの長期化する引きこもりを「大きな引きこもり」とするならば、不登校は「小さな引きこもり」である、と。この「小さな引きこもり」が十分にできなかったり、無理して「いい子」をがんばって演じ続けてきた子が、大人になってから「大きな引きこもり」に入る傾向がある、そう言ってました。
親として大切なことは、我が子の不登校・引きこもりを、無条件で認めてやり、子どもが引きこもることに関して、何も罪悪感とか苦しみとか感じなくていいよう、堂々清々・豊に、ゆったりと引きこもることができるよう、経済的に保証してあげること。それから、決して子どもの前に出て、行くべき道をあれこれ指図せず、子どもの後ろからついていって、そっと静かに見守る態度が重要。高岡先生は、そうおっしゃいました。
●この講演を聴いて、ぼくが感じたことは、精神科の医者って、言葉のレトリックがじつに巧いということです。話を聴いているうちに、まんまと言いくるめられてしまっている自分に気がつくんですね(^^;) それって、新興宗教の教祖の「お言葉」と、そうは違わないんじゃないかな。まぁ最終的に、信じた信者が彼の言葉によって救われれば、それは決して「まやかし」ではないと思います、確かに。これって、かなりひねくれた言い方ですが、高岡先生のこの解法が結局は正しいのだ! そう感じたことは間違いありません。
それから、もう一つ確信を得たことは、引きこもりって『三年寝太郎』のことだったんだ!と解ったことです。日本には、江戸時代の昔から「引きこもり」は存在していて、昔話にも登場していたのです。この昔話で大切なことは、三年寝太郎が働きもせず、ただただゴロゴロ寝てばかりいるのを、とがめもせず認めてあげた彼の両親の存在でしょう。
そうは言っても、もしも我が子が不登校になったならば、ぼくは「三年寝太郎」の父親のように振る舞えるのだろうか? まったく自信はありません。
『ケータイを持ったサル』正高信男(中公新書) 2003/10/17
●TSUTAYA伊那店へ行って、『タケモトピアノの歌』を買ってきました(^^;; ¥980(税込み)。驚いたことに、CD&DVD2枚組なのです。しかも、どちらも30分収録時間があるのです。15秒のスポットCMが2種類、代わりばんこに繰り返し繰り返し「延々と」30分間ただただ続くんです。すごいなコレ(^^;)
DVDで、何度もCM映像をながめて、何故これが子どもに受けるのか考えたんですが、よく分からない。宇宙人みたいな怪しげなレオタードを着て「くねくね踊り」をする4人のオネーサンたちが、やっぱり子どもの目を引きつけるんじゃないかなぁ。少なくとも、武富士のレオタード軍団よりも、インパクトあるもんなぁ。
●京大・霊長類研究所・教授、正高信男先生の新作が中公新書から、またまた出ました(^^) 本のタイトルは、栗本慎一郎センセイの出世作『パンツをはいたサル』をもじって、『ケータイを持ったサル』 。
それにしても、このyn0711さん、キビしい評価だなぁ。でも、そんなに真面目に正高信男・著作を読んじゃダメよ(^^;) 正高センセイは、近頃ますます先鋭化してきていて、大阪人の毒舌・辛辣の牙を研ぎすましています。その論理体系は、喧嘩ごしで強引。最後には自分の得意分野の「サル」に何でもかんでも関連つけて結論をだすという、ほとんど「トンデモ本」の領域(いや、悪口で言ってるんじゃなくてね)に突入しました(^^;)
ぼくは、だからこそ、正高先生の本は面白い!そう断言してしまうのです。本を読んで、何か有意義な最新の知識を仕入れようとしても、それは無駄です。われわれは、正高先生のあの「論理的なようでいて、単なる言いがかりに過ぎない詭弁すれすれの弁舌」を楽しめばよいのです。そんな観点で読めば、近頃これほど面白い本はありませんでっせ(^^;;
財津一郎『タケモトピアノの歌』 2003/10/16
●以前「探偵ナイトスクープ」で取り上げられて話題を呼んだ、あの中古ピアノ買い取り専門店「タケモトピアノ」のテレビCMが、先月CD(テレビCMのDVD付き)発売されたそうだ。財津一郎が例の独特な抑揚をつけた声で「ピアノ売ってチョウ〜ダイ!」と歌うのを聴くと、なぜかさっきまで「ぎゃーぎゃー」泣いていた赤ちゃんがみなピタリと泣きやみ、テレビを食い入るように注視するという不思議なCM。
http://www.sanspo.com/geino/top/gt200309/gt2003092002.html
さっそく買ってこなくっちゃ(^^;)
ダッチオーヴン料理(第3弾!)は、ナンを焼いてみた 2003/10/13
●昨日の日曜日は、妻がいとこの結婚式で昼間留守だったので、子どもを連れてベルシャインまで歩いて買い出しです。今回は、インドの「ナン」を作ってみようと決めていたので、必然的にインドカリーも作らなければなりません。さて、どうしたものかと、ベルシャイン食料品売場のインスタント・カレーの棚を見上げたら、S&Bすぱいすぴーぷる・手作り用「ケララカレー」というのを発見しました。ローレルの葉っぱに、鷹の爪、シナモンスティック、粒胡椒、クミンもそのまま付属しています。
これは期待できそうだぞ! と買い物かごに入れ、同じ棚に並んでいた「炒め済みのタマネギペースト」も買って帰りました。あとは、鶏の手羽とセロリ、さつまいも(これは今日、石焼き芋にしたのです)。人参、生姜、ニンニク、それからリンゴは家にありました。
■家に帰って、まずは「ナン」の生地つくり。薄力粉+牛乳+ヨーグルト+卵1個+ベーキングパウダー、重曹、塩、砂糖、サラダ油を混ぜて生地をこねます。ところが、どこかで何かの分量を間違えたのか、べちゃべちゃで、こねるどころではないのです。しかたないので、薄力粉をどんどん足して、なんとか生地にまとめたのですが、考えてみたら、自分ではパンて、一度も作ったことないんですね。大丈夫だろうか? ま、3時間そのあと生地を寝かせろと、テキストに書いてあったので、子どもたちを連れて三峰川河川敷の公園へ自転車に乗りに行って時間をつぶしました(^^;)
カレーの準備が整ったころ、ちょうど3時間が経過。子どもたちにも手伝ってもらって、生地をピンポン玉の大きさにちぎり、平らにのばします。200℃以上にあたためたダッチオーヴンにオリーヴオイルを少しひいて、伸ばした生地を鍋の底に入れます。蓋をして、炭をのせ、15分間焼きました。

■出来上がりは、インド料理の「ナン」とはずいぶん違う、硬めのホットケーキという雰囲気になってしまいましたが、カレーの方が予想外に美味しくて、なんとなく大好評を得ることができました(^^;) この、S&Bすぱいすぴーぷる・手作り用「ケララカレー」はオススメです。
●評判がいいのに気をよくして、今日の午前中には、ダッチオーヴンで「石焼きいも」を作ってみましたよ。ほんとは、ホームセンターへ行って「小粒の玉砂利」を買ってくればいいのですが、面倒くさいので自宅駐車場に敷いてある「川ジャリ」を10数個拾ってきて、よく洗ってから鍋の底に入れました。さつまいもを入れて、弱火で40分近く加熱したのだけれど、仕上がりは今ひとつ。
原因は、どうもサツマイモの種類の選択を誤ったことみたい。まぁ時には失敗もなくっちゃね(^^;;
『子どものスイッチ』斎藤次郎・福尾野歩・増田善昭(雲母書房) 2003/10/12
●「メーリーゴーランド」のサイトで、『子どものスイッチ』 斎藤次郎・福尾野歩・増田善昭(雲母書房) という本が、この9月に発売になったと知って、あわてて注文しました。昨日、TSUTAYA に届いて買ってきたのですが、予想以上に面白いな、この本。
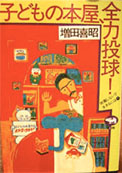
●三重県・四日市の町はずれにある、子どもの本の専門店「メーリーゴーランド」の名物店主・増田善昭さんには、『子どもの本屋、全力投球!』(晶文社) と、『子どもの本屋はメーリーゴーランド』(晶文社)という2冊の著書があって、どちらもスッゴク面白い本でした。
子ども関連の評論を続ける斎藤次郎さんにも、著書はいっぱいある(読んでないけど(^^;;) でも、伝説のバンド「トラや帽子店」の座長として活躍してきた、遊びの天才!福尾野歩さんには、たしかエッセイの著書はなかったはず。だから、野歩さんが語る「子ども論」に、すっごく期待したワケね(^^) 読んでみると、思っていたこととはぜんぜん違っていて、かえって期待以上でした。
野歩さんは、例えばこんなこと、言ってる。
子どもたちを大人の理屈につきあわせている、ってことなんだよね。いまの子どもたちは、もう5歳児から、それをしちゃうんだよ。子どもって、「やだもん」とか「うれしい」とか、あるいはなにも言わないで駆け出しちゃうとか、泣き出しちゃうとか、「実」でぶつかってくるもんだと思っていたじゃない。だけど子どもの心にも「虚」の部分はあるわけで、それがどんどん増えて「折り合い」でいっぱいになっている、って感じ。(p43-44)
この間、中学時代の友人で、20年来やくざをしてきたというのが逃げ出してきたんですよ。で、僕に向かって言うの。「自分は、やくざになりきれなかった。母子家庭に育ったけれど、愛のある家庭だった。近所のつきあいもあったし、お前もいてくれたし……。やくざは、やっぱり、人間をどうでもいいと思わないと偉くなれない」って。
それを聞いて、僕は涙が出た。それで、もう一度、地域のことを考えた。僕が育ったころは、みんな貧しかったし暴力もあった。でも愛があったのよ。今はなんでもあるけれど、愛だけがないという状況が多すぎると思う。(p52)
●しみじみ、いいこと言うねぇ。野歩さん(^^)
「この本」に関しては、ぼくが小児科医になった「理由」とも関連する話題が登場するので、次々回くらいにまた取り上げる予定です。
NHK 朝の連続テレビ小説『てるてる家族』は、久々に期待できるぞ 2003/10/09
●10月から始まった、NHK 朝の連続テレビ小説『てるてる家族』が面白い。欠かさず見るのは『さくら』以来。大阪放送局・製作ドラマでは『ふたりっこ』の後は、どれもこれも駄作続きで見る気もしませんでしたが、今回は珍しく出来が良い。なかにし礼 の原作のよさによるのだけれど、すっごくテンポがいい脚本が出色だ。しかも、朝の連続テレビ小説初のミュージカル!
このドラマの本当のヒロインは浅野ゆう子であることが「年増」でちょっと辛いのだけれど、頑張ってるんですよ、浅野ゆう子さん(^^;) ドラマの舞台が、昭和30〜40年代の大阪府・池田市というのもいい。ぼくが子ども時代だった頃のおはなしであることもウレシイ(^^)
しかも、「このドラマはフィクションであり実在の人物とは一切関係はありません」そうテロップは流れるのだけれど、本当は実在のモデルがあって、あの「ブルーライト・ヨコハマ」で知られるいしだあゆみ、石田りえ姉妹、一家の話なんですね。なかにし礼の奥さんが、このドラマの主人公の四女、石田りえだったのです。ちなみに、長女は冬季オリンピックに出場したフィギュアスケート選手、次女がいしだあゆみで、三女は「日清インスタント・ラーメン」の開発に携わった人みたい。
シドニー・オリンピックの水泳背泳ぎで銀メダルを取ったあと、燃え尽きちゃって女優に転向した「田なんとか」さんが今日から登場しましたが、彼女だけはミス・キャストだな、どう考えても(^^;)
今日は「ローストチキンに挑戦だ!!」 2003/10/05
●今日の日曜日は、朝からものすごくいいお天気だったのだけれど、伊那市主催・伊那市医師会ほか共催「いーなちゃん祭り」が、勤福体育館で行われるため、開会式の9時に間に合うように、白衣を着て8時40分に家を出ました。医師会からは、林整形外科・先生と、河野先生と、ぼくが出席して、医療相談と献血立ち会いを行いました。
「小児科医による絵本の読み聞かせ」を企画して、ぼくは一応「絵本を20冊」ほど会場に持ち込んだのですが、なんだか場違いな雰囲気で、どうも子どもはそんなに来ないというお話だったので、絵本の読み聞かせは早々にあきらめて、献血立ち会いにお昼まで専念しました。40人弱の方が献血に来てくださいましたよ(^^)

●献血会場でそっと、妻に携帯でメールしたのですが、返信をちゃんと確認しなかったために行き違いになってしまい、午前中、大芝公園でトンボ採りをしていた子どもたちは、お昼過ぎに南箕輪から勤福体育館にやって来ました。でも、おとうさんはすでに仕事を終えて、自宅に帰った後だったのでした(^^;;
●これから遠出は無理なので、とりあえず、アピタへ買い物に出かけました、家族みんなで。じつは、「今度の日曜日にはおとうさんが、ダッチ・オーヴンでローストチキンを作るぞ!」そう宣言してあったので、前日のうちに、鶏まるまる一羽を、妻は「鳥肉屋さん」から、1300円ちょっとで買ってきてくれてあったのです。
だから、アピタで買わなければならなかった食材は、ニンニク・セロリ・トウモロコシ・ジャガイモ・ニンジン・レモン、それに「ワイルド・ソルト」。あ、あとはビールとチューハイね(^^;)
帰宅後キッチンに立ったぼくは、まずはニンニクの皮をむきます。それからレモンを2個絞って、鶏肉に漬け込みます。水分を切ってから、塩コショーを鶏肉の「外側」と「内側」にまんべんなくまぶします。さらに「ワイルド・ソルト」を鶏肉に擦り込みました。鶏のおなかの中へは、ニンニクとセロリの葉っぱを詰めて、爪楊枝で塞ぎます。

プレヒートしたダッチ・オーヴンにオリーブオイルを少しひいて、鶏を入れ、上下に焦げ目をつけてから一度取り出します。オーヴンの底にセロリの茎をひき(2本分)その上に鶏肉を載せ、蓋をして、弱火で60分焼きます。キッチンタイマーが鳴ったら、蓋を開け、ジャガイモ・ニンジン・トウモロコシを隙間に入れます。再び蓋をして、蓋に「炭火」を置き、野菜に火が通るまで、さらに30分、弱火で焼きます。
タイマーが鳴ったら、蓋を取ってできあがりです(^^) 12インチ(30cm) のオーヴンだと、余裕ですね(^^;;
●家族4人で「鶏一羽まるごと」食べ切ることはできませんでした。いや、美味しかったんですけどね、半分がやっと(^^;) 子どもらも、先週の「鯛」ほどは食べなかったな。それから、思いのほか塩味が効いていなくて「うす味」でした。もうちょっと研究の余地がありそうです。でも確かに、レンジのオーブンで鶏肉を焼くと、もっと「パサパサ」するんだけれど、ダッチ・オーヴンを使うと、しっとり・ふっくら仕上がりますよ(^^)
先生はなぜ小児科を選んだのですか?(その3) 2003/10/04
●さて、じゃぁその、中学2年生の小児科医志望の女の子に、高遠へ向かう車中、ぼくは何て答えたのか?
それはね、ちょっと秘密(^^;;
その代わりと言ってはなんだけど、2002年3月に、長野県内の小児科医を結ぶメーリングリストの中で、ぼくが発言した内容を、こちらに転載させていただきます。これで勘弁してくださいね(^^;;
北原@伊那市です。
先週の日曜日に松本へ「モンスターズ・インク」 を見に家族みんなで行ってきました。
映画を見終わって外に出るなり、5歳の長男は目をウルウルさせながら「おとうさん、いい話っだったねぇ」そう言いました。じつは父さんも、眼鏡の奥は涙がいっぱいで、ちょっとだけ恥ずかしかったのですが……
やっぱり「ピクサー」 の映画は凄いですね。アメリカっていう国は、ブッシュとかいう、どうしようもない「おバカさん」 が大統領の、冬期五輪を平気でアメリカ国体にしてしまう、とんでもない国ですが、その一方で、カリスマ言語学者にしてアメリカの良心とも呼ばれるチョムスキーが自由に発言できるし、ピクサー&ディズニーが倒産した「エンロン」 を正面から批判した映画を「子ども向けアニメ」として上映できるアメリカという国の底力には、やはり凄いものがあるなぁ、と尊敬してしまう私でした。
「モンスターズ・インク」の構造は「千と千尋の神隠し」 とまったく同じです。人間の少女が間違って「魔界」 にまぎれこんでしまうお話なのです。でも、見終わった感想はまったく異なります。何故でしょうか?
それは「視点」が異なるからです。「千と千尋」は10歳の少女の視点から、「大人なんていらないよ!」 っていう映画でした。ところが、「モンスターズ・インク」は、大人の視点から「やっぱ、子どもって可愛いね!」 という映画なんですね。
アメリカも日本も、子どもには冷たい国だと思います。特に、自分の子どもを連れて電車に乗ったり、図書館へ行ったりすると、周りの冷ややかな視線を常に意識してしまう毎日です。
そうは言いながら、ぼく自身、自分の子どもが生まれるまでは、子どもには冷たかったです。正直に言えば、子どもが嫌いだったのです。では、なんで小児科医になったのでしょうか? それは自分でもよく判りません(^^;)
よく、「子どもが好きだから、小児科医になりました」 って言う人いるでしょう? でも、それって本当なんでしょうか? 子どもって、悪意に満ちてるし、うそつきだし、意地悪だし、あまのじゃくだし。自分の子どもでもない限り、絶対に好きにはなれない、ぼくはそう思っていました。昔は。
でも、自分ちの子が「かわいい」と思えるようになると、不思議と「人ん家」の子どもも可愛く思えるようになるんですね。そうしてぼくも、最近ではすっかり「子ども好き」です(^^;;;
とにかく、この映画に登場する2歳の女の子「ブー」って、たまらなく可愛いのです。しぐさとか、表情とか、2歳児をよく観察していますね。感心しました。一つだけよく分からなかったのは、アメリカ映画なのに「ブー」髪は黒髪で、顔つきはどう見ても東洋人(もしくはメキシコ人?)なんですが、これには何か大きな意味があるのでしょうか?
いずれにしても、この映画を見終えた大人は、絶対に幼児虐待はできないと思いますよ、ホント。
●どうして小児科医になったか? よりも、いま現在、小児科医として充実した毎日を送っているかどうか?訊くことのほうが、絶対に意味があると思うのは、ぼくだけでしょうか?
ぼくは自信を持って「今は」こう言えます。
小児科医になって、ほんとよかった。小児科医は、ぼくの天職だ! と。
(まだ、ちょっと誤解を生みそうな話題なので、もう少し続く予定)
先生はなぜ小児科を選んだのですか?(その2) 2003/09/30
●日本外来小児科学会が編集した『小児プライマリ・ケア虎の巻』 (医学書院)という本があります。最近、DVD付きの『龍の巻』も出ました(こっちの方が「スグレモノ」だと、ぼくも思う)何故って、このDVD、上伊那医師会付属准看護学院での小児科学の講義に明日も使わせてもらうのですから(^^;)
その『虎の巻』の方の最終章に、「若い人へのメッセージ」山中龍宏 が載っています。そこには、こんなことが書いてある。
初対面の人に「私は小児科医です」と言うと、「なぜ小児科を選んだのですか?」とよく聞かれる。内科医や外科医も「なぜ、その科を?」と聞かれるかもしれないが、小児科を選択したことへの興味より関心は低いように思う。そのベースには、「大人であれば話が通じるのに。わざわざ、話もできない、理解力に乏しい子どもを見る仕事を選んだにはなぜですか?」と聞きたいのだと思う。そして、「子どもが大好きだから」という答えを暗に期待しているように思う。
小児科医の集まりでは、お互いに、なぜ小児科医になったかを聞くことはない。いろいろな答えがあるのだろうが、胸を張って「私は子どもが好きだからです」と答える小児科医はほとんどいないのだということを最近知った。育児雑誌ライターで、全国の百人以上の小児科医を取材してまわった人から聞いた話である。
初対面の小児科医を短時間に評価するコツは、にっこりとして、どうしても知りたいという雰囲気を出しながら、「先生はどうして小児科医になったのですか?」と聞けばよいと言っていた。
ほとんどの小児科医が答えに詰まったり、答えをはぐらかしたりするとのことである。口ごもりながら「まあ、なんとなく…」「子どもは嫌いではないし…」「小児科は臓器じゃなくて、全体をみることができるから」「小児科にいけば、いろいろな分野があって、その中から選択できると思って…」と答えたり、やや斜に構えた人では「私は、子ども以外、大人とは話が出来ないので…」「あの科も嫌、この科も嫌といっていたら、小児科が残っただけ」などという人もいるようだ。このライターは、こうして出会った小児科医の値踏みをしているようだが、なかなか的確な判定法だと思う。
ぼくはこの部分を読んで、「えぇっ!」とビックリしてしまったのです。山中先生! マジで本当に「的確な判定法」だと思っているんですか? じゃぁ、「ハイ! ぼくは子どもが大好きで大好きで、医学部に入った時から小児科医になることを心に誓っていました!」と言った小児科医なら信用できるのでしょうか?
それって、絶対に間違っている! と、ぼくは思うぞ! (まだまだ続く)
「ダッチ・オーブン」を買った! 2003/09/28
●前から欲しかった、憧れの「ダッチ・オーブン」を、とうとう買ってしまった。本当はね、松本の「石井スポーツ」で見た「LODGE社製・10インチ・ディープキャンプ」が欲しかったのだけれど、1万円もしたので、その時は躊躇して止めちゃったのでした(^^;)
で、結局購入したのは、国産(新潟県三条市・パール金属)のCAPTIN STAG 製「12インチ・ディープ(足なし)」。テルメの近くのディスカウント・ショップで、66%引きの\3,980。 品質は? だけれど、自宅キッチンのレンジでも使えるように「足なし」のほうが便利かもしれない、そう思って購入することに決めました。
「ダッチ・オーブン」は、買ってきてそのまま直ぐには使えません。シーズニングをしなければならないのです。今日の日曜日の午前中は、この「シーズニング」に費やされました。まずはクリームクレンザーで、工場で塗られてきた「錆どめワックス」を落とします。その後、オリーヴオイルを薄く塗ってはレンジの強火で焼く作業を3〜4回繰り返します(ふた・なべ本体とも)。そうすると、購入時のメタルグレー色が、次第に黒く変色してくるのです。これがウレシイ(^^)
手入れの良い使い込んだ「ダッチ・オーヴン」は見事に黒光りしていて、ブラック・ポットと呼ばれるのだそうです。それが、この鍋の持ち主の誇りなんですって。日本で初めてダッチ・オーヴンを紹介・伝道した菊池仁志さんの話では、彼の友人でネバダ州に住むアメリカ人は、こう言ったのだそうです。
「女房とピック・アップ・トラックは貸すが、オレのブラック・ポットは駄目だ」
●珍しく、おとうさんがキッチンに立っているので、子どもたちは興味津々。「夕ご飯は、おとうさんが作ってくれるの? 凄いな! こんなの初めてじゃない?」 確かに、奥さんが寝込んだ時くらいしか、最近は料理を作ってない(^^;;
さて、じゃぁこの「ダッチ・オーブン」を使って、何を作ろうか? ということになったのだけれど、昼飯にケンタッキー・フライドチキンを食べてしまったので、ダッチ・オーブンの初心者向き定番の「蒸し鶏」は今回はパス。となると?と30分考えて、「鯛の塩釜」に決定いたしました(^^)
さっそく「アピタ」まで買い出しです。22cmくらいの小鯛 (\360) を2ひき、北海道利尻昆布、それに粗塩2kg。
帰宅後、子どもといっしょに「卵4個分の白味」と「粗塩 1.5kg」をよく混ぜて、2cmくらいの深さでオーブンにひきつめます。その上に、水で戻した昆布を鯛にくるんで置き、残りの塩を上から被せて押さえつけます。ふたをして、レンジにかけ、中火で50分。これで出来上がり(^^)
これが思いの外好評だったんです。塩の中から鯛を掘り出す作業が、まるで化石の発掘みたいで、子どもたちに大受けだったし、なによりも鯛がめちゃくちゃ美味しかった!!
「おとうさんって、スゴイね!」
息子のこの「ひとこと」に、すっかり気をよくしたおとうさんは、さて、来週は何を作ろうか? と、今から思案しているのでした(^^;)
先生はなぜ小児科を選んだのですか? 2003/09/26
●昨日の木曜日は、伊那東部中学校の2年生の女の子が2人、職場体験実習として、朝8時から当院にやって来ました。職場体験の中学生を受け入れたのは、今年が初めてで、この7月末には、夏休みに入った伊那中学校2年生の、看護師志望の女の子が2日間やって来ました。ナースのユニフォームを着て、キャップもかぶって、小児科外来の介助をしていただきました。
ところが今回は、2人のうちの1人は看護師志望だったのだけれど、もう1人はなんと小児科医志望だったのです。ふたり来て、ひとりにナースのユニフォーム、もうひとりにはケーシー白衣という訳にもいかず、結局、中学の青いジャージにエプロンという「いでたち」で登場していただくこととなりました(^^;)
午前中は外来の予診・診察介助と、処置(吸入・点滴・採血)、薬局・会計の見学をしてもらって、お昼のお弁当の後、2・3歳健診のある高遠町保健センターへ、ぼくが運転するトリビュートに乗ってもらいました。高遠までは、車で15分かかります。車中、いやーな沈黙が支配しました。ぼくはヤバイな、と思ったものの、中学2年生の女の子にどんな話題を振ったらいいのか皆目見当もつかなかったのです(^^;)
で、仕方なくぼくは「なにか質問はある?」って訊いたんですね。そしたら、例の小児科医志望の女の子がこう言ったのです。
「先生はなぜ小児科を選んだのですか?」
ぼくは「うっ」と、思わず言葉に詰まってしまいました(^^;)
な〜んでか?
(つづく)
その後の「恐るべきさぬきうどん」 2003/09/24
●千趣会の月1回の宅配「恐るべきさぬきうどん」 が、この9月で12回完了となりました。その有終の美を飾ったのは『善通寺・山下のうどん』。今から5年も前に、ネット上で「さぬきうどんの魅力」を抜群の文章力でもって表現したさとなお・著「うまひゃひゃ さぬきうどん」でも、p121 で、このように絶賛 されています。
そして特筆すべきはその「舌触り」。
まさに絹の舌触りだ。
であるからして、歯の攻撃をニュルッと逃れて、口の中で暴れまくってくれる。
ほとんど「口内暴力」。
ホンモノの打ちたての山下のうどんは、かように美味いらしい。でも、日清冷凍食品が実際は作っている「千趣会・恐るべきさぬきうどん」の冷凍宅配が、ほんとうに美味いかどうかは、正直かなり疑問でした。だって、先月の「がもう」のうどんはハズレだったから。
ところが、この「善通寺・山下」の冷凍うどんが、もうめちゃくちゃうまいのです!! 感動しました。マジで。
●千趣会では、この「恐るべきさぬきうどん」の第2弾!シリーズ化をもくろんでいる模様です(^^;)
月々2650円も払って、冷凍うどん8玉とつゆが送られてくるだけなので、スーパーで加ト吉「冷凍さぬきうどん」を買ってきたほうが絶対に安い! だけどもさ、わざわざ四国・香川県まで行かなくても、名店の味の雰囲気だけでも体験できれば、これって楽しいんじゃないかな(^^)
ぼくはさっそく、千趣会に「さぬきうどんの会・第2弾」もちろん注文しましたデスよ(^^;;
小鳩園で「お話」をしてきました 2003/09/19
●今日の昼休みは、伊那市水神町にある発達障害児の母子通園施設「小鳩園」へ行って、通園しているおかあさん方に「お話」をしてきました。園医として年1回行っているのですが、毎回、前半はぼくが好き勝手に話をさせていただいて、後半はおかあさん方からの質問に答えるといったスタイルでやっています。
今回は「スローライフ(Slow Life)のすすめ 〜 がんばりすぎないで!おかあさん」 というテーマで、おはなしするつもりだったのですが、準備不足もあって、例によって何だかワケわからない、とりとめのない話になってしまいました。加島祥造さんの『タオ・ヒア・ナウ』から「たかのしれた社会」と「<汚い>があるから<美しい>がある」を朗読して、この『タオ・ヒア・ナウ』が大好きな、ダウン症の青年玄ちゃんの話になって、映画『八日目』 に主演した、ダウン症の役者パスカル・デュケンヌのことを話しました。
それから、ぼくが大好きなハードボイルド作家、打海文三の代表作『時には懺悔を』 (角川文庫)に登場する、二分脊椎による重症水頭症のタフネス新ちゃんの話になりました。障害はあっても、きっと神様は「この世に、この子が存在することが必要に違いない」そう思われて、この子を使わされたのです。この子によって、周りで生きているみんなが励まされているんですよ。
そういう話をしたかったのですが、何だか取って付けたような感じになってしまって、聴衆のおかあさんたちがどんどん引いてゆくのが分かったんですね(^^;) これはマズイ! と、あわてて軌道修正することにしました。必殺!「絵本の読み聞かせ」作戦です(^^;)
おかあさんだけが全てを背負い込まないで、おとうさんを上手にてなづけて! という願いを込めて、まず最初に読んだのは『落語絵本・はつてんじん』 川端誠(クレヨンハウス)。おかあさんから、クスクスって笑い声がもれてきて、少し受けた。よかった(^^)
これに気をよくして、勢いで、新作の『コップちゃん』 中川ひろたか・文、100%ORANGE」・絵(ブロンズ新社)と、『はくちょう』 内田麟太郎・文、いせひでこ・絵(講談社)を読んでみました。これはどうだったかな? 残念ながら、おかあさんからは絵本の感想は訊けませんでしたが(^^;)
でも、園長先生が「大人になっても、絵本を読んでもらうって、気持ちがいいね!」そうおっしゃってくれました。とっても、うれしかったな(^^)
ヴィレッヂ白州 ・ゆーとろん・ボーネルンド・LEGO 2003/09/15
●連休だというのに、何も予定がありませんでした。小淵沢方面にでも行こうか、ということになって、土曜日に何軒かホテルの空室状況を訊いてみたけれど、どこも満室。仕方ないねと、一度はあきらめたのですが、日曜日の朝になって、富士見に住んでいたころ一回だけ行ったことのある「ヴィレッヂ白州 」 に電話してみたら、当日でもコテージに空きはありますよ、との返事。急きょBBQセットを車に積み込んで出発と相成りました(^^;)
諏訪南インターで中央道を下りて、まずは富士見パノラマスキー場近くの「ゆーとろん・水神の湯」 へ。ここの露天風呂は、浴槽がいくつもあって広々としていてホント気持ちいい(^^) ぬるめだけれど、硫黄が効いていて体の芯からポカポカ温まるのです。由貴奈ちゃんのおとうさん、おかあさんにも久しぶりにお会いできました。よかったな(^^)
新しくできた「富士見コープ」で食材を仕入れて、15時半過ぎに「ヴィレッヂ白州 」到着。池が2つあるのですが、以前来た時に、上の池にイモリがいっぱいいたのを覚えていて、虫網の他に「水網」も持ってきたのは正解でした。子どもたちは大喜び。
下の池にはマスとハヤがいて、今朝早くに行って釣りをしました。30分ほどの間に、10cm前後のハヤが次々とかかりましたよ。マスはダメだったけど。朝食の後、山の上の展望台まで、徒歩で林道を片道40分。頂上から八ヶ岳方面を眼下に眺望できましたが、ずいぶんと疲れたな(^^;) 山を下って尾白川の滝を見に行こうと予定していたのを取りやめて、八ヶ岳リゾートアウトレットへ。連休のせいか、なんだかやたらと混んでいましたよ。駐車場も満杯、道路も渋滞。
お目当ては、一番上の「北側サイト」に8月オープンしたばかりの「ボーネルンド」 です。松本の「アイシティ井上」には以前から店舗があるのですが、売場面積は倍くらいあって、品数も豊富。ただし、アウトレット内の店なのに、バーゲン商品は皆無 なんです。なんか強気の商売してるなぁ。そのあたり、開設当初よりある「LEGO ショップ」とはえらい違いだ。
子どもらは、レゴ・バイオニクルを買ってもらって大喜び。帰りは、鉢巻き道路を原村にまわって、八ヶ岳小さな絵本美術館に寄って「林明子・絵本原画展(後期)」を見てから家路につきました。
左利きと両手利き 2003/09/13
●『右脳ってなあになぜ子育てに大切なの』 金子満雄・著(IUP)1995/07/25 には、面白いことが書かれています。現在「品切れ」ですので、少し長めですが以下引用させて下さい。
■言葉の中枢は左脳に配置し、音楽の中枢は右脳に配置しようという脳の働きの機能分化(側性化)が始まるのは4〜6歳と言われています。
そのとき、言葉の機能が全部左側に集まってきて、左脳で言葉を聞いたりしゃべったりすることのすべてを行うのが、純粋な右手利き なのです。逆に、右脳に言葉の機能全部が集まってしまうと、これが純粋な左手利きになります。
ところが、純粋な右手利きや純粋な左手利きの人は案外少ないものです。 純粋な右手利きは男性のみにあり、その35%くらいに、また純粋な左手利きはわずか2〜3%くらいだろうというのが、私たちの研究からの大雑把な見方です。
残りの人は両手利きであり、つまり両脳利きと考えられます。女性は原則として両脳利きに作られていると思われます。ただし、その際も「8 - 2」の右利きであったり、「7 - 3」の右利きであったりと、その比率の違いもあるらしいというのが私たちの見方です。
8 - 2の右利き とは左脳に8割の言語野があり、同時に右脳にも2割の予備言語野(スペアタイヤのように)があることを意味します。その場合、普段は左脳で言語を操っていますが、一旦、そこに故障でも起こると、右脳の予備言語野が働き始めるのだと私たちは解釈しています。(普段でも予備言語野が補助的に働いているかどうかについては、まだ私たちは結論を得ていません。しかし、最近、米国からの PETスキャンによる言語野の研究で、女性では両方の脳が同時に活動している写真を報告しているようです。)
左利きについては本来、左寄りの両手利きであることが以前から気付かれていました。その中のごく一部に純粋な左手利きがいると考えたほうがよいでしょう。
■では、純粋の右利き、左利きと両脳利きとでは何が違うのでそゆか。人生にどんな影響があるのでしょうか。(中略)
たとえば脳の中に出血して左脳がこわされた場合を想定してみてください。純粋な右手利きの人の場合は左脳に言語領域のすべてが配置してありますから、完全な失語症になって、言葉が戻ってくる可能性はほとんど無くなってしまいます。ところが両脳利きの人の場合は、もし言語領域の振り分けが左脳に優勢に7 - 3だったとすると、左脳の7割がこわされても右脳にまだ3割が残っているので、そこで言葉を復活することができるのです。(中略)
■右手利きと左手利きを男女比でみると、純粋な右手利き、純粋な左手利きはほとんどが男性で、女性はほとんどが両手利きだと考えられています。男女の間でこのように側性化が異なって進行するのはなぜでしょうか。それは系統発生的にも雄は受精さえすればいつ死んでも構わないように作られていますが、雌は受精したあとも妊娠、出産、子育てと重要な使命が課せられているために「簡単にはくたばらないシブトサ」が付加されているという、いわば種の宿命のようなものに起因すると考えたほうがよさそうです。
さて、男性と女性のこのような違いは専門教育のあり方にも影響します。たとえば、音楽家になりたいというような場合に、純粋な右手利きの人は右脳に音楽領域のすべてがあると仮定されるので、100%の能力で勝負できるのです。ところが、両脳利きの人、たとえば左脳優勢の7-3の人の場合は音楽については右脳に7、左脳に3が配置してあると想定されます。つまり、実質は70%で勝負しなければなりません。プロの演奏家や作曲家としての競争では必然的に100%勝負できる 人のほうが有利と考えられます。(中略)
しかし反面、スペシャリストと言われるような人たちは専門バカという言葉があるように、ある分野ではすばらしい能力を発揮しますが、ほかの分野では全然だめという人が少なくないのも特徴のようです。音楽の分野ではあのような天才的手腕を発揮したモーツァルトでも、お金の計算はサッパリ駄目だったり、社交の場では常識がなく、イタズラッ子ぶりを発揮したことはよく知られています。女性は一般的に常識的で、判断も中庸を得ている場合が多く、生活態度にも偏りがないのも上の見方と合致するようです。
世の中にはスペシャリストも大切ですが、ゼネラリストも必要です。
「第3章 脳が決める右利き・左利き」(p43〜50)より引用。
左利きに関する「参考文献」 2003/09/10
●今回の「左利き」についての論考は、以下の本を参考にし、一部を引用させていただきました。
・『続・子育ての医学』 馬場一雄・著(東京医学社)(p46〜48) 利き手の発達
・『左利きで行こう!』 リー・W・ラトリッジ著、丸橋良雄・訳(北星堂書店)2002/06/05
・『左ききでいこう!』 フェリシモ左きき友の会&大路直哉・編著(フェリシモ出版)2000/07/01
・『脳と心の地形図』 リタ・カーター著、藤井留美・訳(原書房)1999/12/10
・『右脳ってなあになぜ子育てに大切なの』 金子満雄・著(IUP)1995/07/25
・「小児期双生児の利き手について」大木秀一『チャイルドヘルス6月号』2003/Vol.6/No.6(p53-56)
<閑話休題>
●先日、岡谷市の「イルフ童画館」 で伊勢英子絵本原画展を見てきました。『山のいのち』『海のいのち』『水仙月の四日』『風の又三郎』『雪女』『よだかの星』からの原画と、あのグレイや、雲が鉛筆で描かれた実際のスケッチブックが数点、それから『レクイエム』と題された、大きな洋画が1点、ひとつの展示室にまとめて展示されていました。
8月31日には伊勢英子さんが来館して、展示室で実際に絵を見ながらのギャラリー・トークが行われたそうです。ネットで検索したら、
茅野市在住(?)のあさがおさんのHPに詳細なレポートが載っていました。これはありがたいです。
●イルフ童画館となりの市営立体駐車場は、なんと5時間無料なので、このまま帰るのはもったいないと、近くの岡谷スカラ座へ寄って、話題の『パイレーツ・オブ・カリビアン』を観てきました。いや、面白かった(^^) エンドロールが流れても、最後の最後まで決して席を立ってはいけない、そう外来小児科MLで聞いていたのが正解でした。怖いけれどもまた見たい。ジョニー・デップ がいいね。『ギルバート・グレイプ』『シザーズ・ハンズ』の頃からのファンです。ところで、子どもぬきで妻と映画に行ったのは、7年前の『Shall we ダンス?』以来だそうです(^^;;
子どもの利き手はいつごろ決まるのか? 2003/09/08
●ところで、宮澤賢治『セロ弾きのゴーシュ』の「ゴーシュ」って、どういう意味があるかご存知でしたか? じつはフランス語で「左」のことを「ゴーシュ」というのです。転じて、英語圏では「不器用な」という意味で使われています。イタリア語で「左」を表す「シニストロ」という言葉には、「不吉な」という意味もあるんだそうです。
日本語でも、「左」はあまりいい意味では使われません。左前・左遷などなど。 左翼・左党が「悪い意味」かどうかは分かりませんが(^^;)
●職業別「左利き」頻度調査って調べた人がいます(^^;) 正確には、職業ではなくて大学の専攻科目は何か? という調査なのですが、オハイオ州立大学の研究員、キャロル・フライさんが、大学在籍366人の学生の「専攻科目と利き手」の関連を調べたのです。その調査結果は以下のとおりでした。
「専攻科目」 「左利きの学生の割合(%)」
---------------------------------------------------
法律 21.7
音楽理論・作曲 19.4
建築 17.4
造園術 15.6
工業デザイン 11.4
会計学 9.3
細菌学 7.5 %
---------------------------------------------------
会計士さんに「左利き」が少ないのは、すごくよく解るよーな気がしますね(^^;;
●さて、子どもの利き手はいつごろ決定されるのでしょうか?
母親の胎内で、胎児は「指を吸っている」ことが、超音波診断で観察されています。ほとんどは「右手の指」を吸っていて、左手を吸っている胎児は約8%にすぎないことが確認されています。この数字は、一般的に言われている「左利きの頻度」と一致しているのですが、胎児の段階ですでに「利き手」が決定しているのかどうかは、科学的にはまだ証明されていません。
生まれてきた赤ちゃんは、目の前にいるおかあさんのまねをしながら、次第に発達して行きます。目の前の母親は、いわば「鏡」みたいなものですから、母親が「右手」を動かせば、赤ちゃんは「同じ側の左手」を動かすことになります。ですから、この時期の赤ちゃんが左手を主に動かしているといっても、左利き であるというわけではありません。
●今から45年も前に、この問題に関しての調査研究成果を論文にまとめたアメリカの発達心理学者がいました。アーノルド・ゲゼルとルイーズ・エイムスの2人です。
その論文の結論によると、成長後にはっきりとした右手利きになった子どもでも、小さい間、ことに乳児期には、主として左手を使ったり、両手利きの時期があったりで、何回も利き手の交代ないし移動が認められる。満2歳ころになると、右手利きであることが、かなりはっきりしてきますが、その後、3歳前後にもう一度両手利きの時期を経過した後、4歳頃になって、やっと利き手が固定してくる。そう言っています。
ただ、ゲゼルは、この論文の最後で面白いことを言っています。一般に、生後3カ月未満の赤ちゃんは、眠る時に、顔を、右か左か、どちらか一方に向けているものですが、この向きぐせから将来の利き手を予測しうる場合が多いというのです。すなわち、右側を向いて眠る赤ちゃんは、右利きに、左側への向きぐせの強い子は、左利きになるというのです。
確かに、うちの次男はたいてい「左向き」で寝ているし、ぼく自身「右向き」では寝にくくて、寝付けない夜には「左向き」で腕組みして横になります。いろいろと面白いね(^^;)
どうして「左利き」は存在するのか? 2003/09/06
●左利きの人が、世の中にどれくらい存在するかというと、歴史的に見てどの時代でも、どの民族でも、総人口の約10%なのだそうです。ちなみに、左利きの男性は、左利きの女性の約1.5倍います。それから、京都大学霊長類研究所教授の松沢哲郎先生のはなしでは、 チンパンジーの左利きは約3割なのだそうです。
なぜ「左利き」になるのか? には諸説あります。利き手は遺伝するという「遺伝仮説」。本来ならば右利きとなるはずの脳のプログラムが、母親の子宮内で(低酸素などの)不利な状況に曝されて、「左脳」にごく小さな損傷が生じたため「右脳」がその機能を代償することとなり、その結果、左利きとなったとするのが「外傷性仮説」。母親の子宮内で、胎児が産生するテストステロン(男性ホルモン)の量と、値上昇のタイミングに問題があったとする「男性ホルモン仮説」 などなど。
それから、もう一つ面白い説があります。一卵性双生児 に特有な現象として「鏡面現象」というのがあります。外胚葉由来の皮膚や神経系の性質が、双子の2人で左右逆転するというのです。例えば、つむじ、指紋の渦の向き・利き手などがそうです。つまり、左利きで生まれてきた人は、本当は一卵性双生児の片割れで、母親の胎内で消滅してしまった右利きの兄弟が実際はいたのだ、という「一卵性双生児・鏡面現象仮説」です。
この「鏡面現象」って面白いですよね。字を覚え始めたばかりの子どもは、よく左右逆さの鏡面文字を書きます。この鏡像書きは、知能障害児や左利きの児で高率に残存すると言われていますが、この左右逆さ文字 を書くことを得意とした歴史的有名人が2人います。1人はレオナルド・ダ・ビンチ、そしてもう一人が『不思議の国のアリス』を書いたルイス・キャロルです。もちろん二人とも左利きでした。
ルイス・キャロルは、『鏡の国のアリス』という続編を書いていますよね。「あべこべ、逆しま、転倒、逆転、こうしたものが満ち満ちた独特な世界に生涯なじんだ。」彼はそう書き残しています。(まだ続く)
「左きき」について考える (その1) 2003/09/04
●ぼくの次男(4歳)は、どうも「左利き」のようです。はたして矯正するべきか? そのまま見守るか? いま、すっごく悩んでいるのです。じつは、僕自身が「左利き」で、今は亡きぼくの父がまた左利きでした。でも、同じ「左利き」といっても、みなそれぞれ微妙に(いや、ずいぶんと)違うのです。
世の中の人が思っているほど簡単には「右利き」「左利き」の2つを、クリアカットに分類することは実際はできません。というのも、純粋な左利きはほとんどいなくて、その多くは「左利きスペクトラム」とでも呼べる、「右」〜「左」の間に連続して存在する「両手利き」だからなのです。
今日は時間がないので、これでおしまい。興味がある方は、以下のサイトを読んで予習しておいてください(^^;;
●「発掘!あるある大辞典」
外来小児科学会 2003/09/01
●すみません、土曜日を臨時休診にして「日本外来小児科学会」に出席するために、仙台へ行ってました。この学会へは、開業した5年前から毎年必ず参加しています。開業小児科医が中心になったまだ若い学会で、実践的でためになる話題が多く、全国から参加してくる小児科医がみな前向きで一生懸命な人ばかりで、参加するたびに「よし、ぼくもがんばろう!」と、エネルギーを分けてもらえるのです(^^)
ただ今年は、土曜日の朝4時半出発で、日曜日のお昼過ぎにはもう仙台を離れなければ、というハードスケジュールだったので、じっくり勉強ができず残念でした。でも、ワークショップを通じて、いろんな先生方とお話しすることができたし、来年も出席しよう。
●仙台の「丸善」で、ここんとこ探していた『カザルスへの旅』 伊勢英子(中公文庫)を見つけて、帰りの飛行機と中央高速バスの中でずっと読んできました。これは凄い本だ。「賢治の修羅」の章を読みながら、泣けてしまいました。この本のはなしは、いずれまた。
●『ER VIII』が、いよいよ「あと2回」で終了します。次回は、例のイズラエル・カマカヴィヴォオレ が歌う「Over The Rainbow」が流れる、ハワイ・ロケの回です。どうぞ、お見逃しなく。
人は音楽なしでは生きられない〜『麦ふみクーツェ』(パート2)2003/08/29
●『音楽はなぜ人を幸せにするのか』 みつとみ俊郎(新潮選書) の中には、こんなことが書いてあります。
音楽文化人類学者クルト・ザックスによれば、人間は幸せな状況だから歌を歌うというよりは、逆に、アメリカの黒人奴隷たちが歌う黒人霊歌やブルーズなどのように、ある種、絶望の淵にあるような状況の方がより「ウタを歌いたくなる」のだという。人生への絶望と諦めがそうさせるのか、あるいは、何としてでも未来へ明るい希望を捨てまいとする願望がそうさせるのか。(p55)
●また、先ほど読んでいた『見えないものを見る 絵描きの眼・作家の眼』 伊勢英子・柳田邦男(理論社) の中で、柳田邦男さんはこんな事を言っています。
音楽というのは、魂の表現であり、魂のコミュニケーションではないかと、私は思っているんです。第一部のモノローグのなかで、大江健三郎さんの「火をめぐらす鳥」を紹介し、魂とは胸の奥に秘められた楽器のようなものだ(人間の胸のなかに秘められた魂という楽器は、ひとりでに歌うのではなく、外部から訪れたものが鳴らすのだ p69)ということを、共感をこめて話しましたけれど、ほんとうにそうだと思う。
もちろん楽器のようなものというのは比喩ですから、魂が姿を見せる、あるいは形や色を見せるのは、音楽に限られるものではなく、人によっては絵だったり、文章だったり、演劇だったり、いろいろです。でも、やはり音楽こそ、最も強く、最も普遍的に、魂の告白、魂の呟き、魂の叫び、魂の呻き、魂の慟哭を、伝えるものだと思うのです。(中略)
どの音楽が、自分の胸に響くかとなると、人によってまちまちです。でも、どのような音楽であれ、人間は音楽なしでは生きられない。魂が沈黙を強いられるからです。(p102,103)
●音楽って何なんだろう? 『麦ふみクーツェ』を読みながら、ずっと考えていました。この小説には、いろいろと印象的なフレーズが登場します。
おじいちゃんは知っている。
降った雨は空へもどせない。ひとはなにかをなくせば、なくなったそこからやっていくほかないって。(p281)
人間、生きてゆくって「そういうこと」の連続だよなぁ。そこに音楽が鳴っているんだ。ただ、その時には「受け身で聴いている」んじゃなくて、できれば自分で歌ったり、演奏したりしたい。しかも、独奏じゃなくて、みんなでユニゾンで歌ったり、楽器を持ち寄って「合奏」すること。それが音楽なんだ、きっと。
『麦ふみクーツェ』いしいしんじ 2003/08/27
●今日8月27日は、宮澤賢治の誕生日です。で、「クーツェ」という、まるで宮澤賢治の童話に登場する人物みたいな変な名前の謎の小人が登場する『麦ふみクーツェ』 いしいしんじ(理論社)のおはなし。
ウェブ本の雑誌での評価は、例によって散々な人もいるけれど、ぼくの感想は一番最後の仲田 卓央さんに近いです。それから、うまくリンクできないのだけれど、過去の新刊めったくたガイドから「いしいしんじ」で検索して、吉田伸子さんの書評を読んでみてください。彼女の思い入れが、ずんずん伝わってくる文章です。この本は、ホントよかった(^^) 個人的には、最新作『プラネタリウムのふたご』よりも好きかもしれない。
というところで、長くなりそうなんで続きはまた明日(^^;;
スウェーデンハウスの医院建築 2003/08/24
●スウェーデンハウスの医院建築のサイトができました。Sweden House for DOCTORです。「北原こどもクリニック」が載っています。よかったら見に行ってみてください(^^)
●千趣会の「恐るべきさぬきうどん」通販。8月は、あの有名な「がもう」でした。期待しすぎたせいもあってか、歯ごたえと弾力性、最後の粘りがイマイチで残念。すこしゆですぎちゃったのかなぁ?
千趣会では、この10月から 新たに「月1回」宅配で「恐るべきさぬきうどん」新シリーズを開始するもようですよ(^^)
自分と同年の有名人 2003/08/23
●自分と誕生日が同じ有名人にどんな人がいるのか? っていうのは、誰もがきっと、子どもの頃からけっこう気にしていることだと思います。ネット上には、ちゃんとこんなデータベースもあります(^^)
●[生年月日(誕生日)データベース]
ただ、このデータベースだと「自分と同い年の有名人」というのは検索できないんですね。
ぼくは昭和33年(1958年)生まれなのですが、ちょうど、森昌子・桜田淳子・山口百恵の「花の中3トリオ」と同学年になります(山口百恵は、昭和34 年の早生まれ)。
宮崎美子や岩崎宏美も同い年。早くから有名になったのはみな女の子ばかりで、男性で成人前から有名だったのは、原辰徳巨人軍監督ぐらいか。いずれにしても、ちょうどぼくらの世代から「早熟のスターたち」がつぎつぎと出てきたこともあって、中学生の頃から同年齢の有名人に興味があったのかもしれません。
●人物の旅 internet-tourist.com
ようやく見つけた「このサイト」では、「生まれ年検索」ができます。えっ! この人が同い年だったの?! という意外な発見があって、たのしいです(^^;)
『グレイがまってるから』伊勢英子(中公文庫) 2003/08/20
●お盆休みに読み始めた『麦ふみクーツェ』 いしいしんじ(理論社)と、『グレイがまってるから』 伊勢英子(中公文庫)を相次いで読了しました。
このところの「マイブーム」は、新鋭作家いしいしんじ氏と、絵本画家伊勢英子さんなのです。特に「森のおうち」 で「いせひでこ絵本原画展」を見てから、すっかりファンになってしまったのでした >伊勢英子さん。
折しも、月刊誌『MOE』(9月号)(p72〜77) に彼女の特集記事が載っていたり、岡谷市の「イルフ童画館」 でも、この8月末から「伊勢英子絵本原画展」が開かれるとの情報。うれしくなってしまいます(^^) それから、『MOE』(2003/1月号)の巻頭に、伊勢英子、きたやまようこ、石津ちひろの3人による対談記事が載っているのですが、いま改めて読み返してみると、いろいろと示唆に富んでいて、とても面白い。
「伊勢」:絵でも文でも私は、自分と質が似てる作家に敏感になってしまう。たとえばバンサンの持っている世界は、私と似ていると思うの。「わたしのきもちをきいて」の2冊なんて、自分が描いたんじゃないかと思ったくらい(笑)。絵に表れる空気や、描こうとしている少女の目線がね。私にはあんなデッサン力はないけれども。
「きたやま」:私、バンサンの絵本はずっと買えなかったの。本屋さんで出会っても、すぐ家に持って帰れないタイプの本なのよ。すごく衝撃を受けるんだけれども、持って帰るのに力が要る。何回も何回も本屋さんで見て、何年がかりでやっと家に連れて帰ったわ。
「伊勢」:わかる。私も「アンジュール」買わなかったもん。もらったから今はうちにあるけれど。
「石津」:私、「ヴァイオリニスト」を読んでいると涙が出てくる。
「きたやま」:あの空気がじかに伝わってきちゃうから、自分も描く者としてすごく浸食されちゃうのよね。単なる読者としては読めない絵本。
「伊勢」:画家の体温みたいなものを感じるよね。
『MOE』(2003/1月号) p14 より引用
●ガブリエル・バンサンが描いた一匹の犬は、心から信頼していた飼い主に無情にも捨てられる。はじめは信じられなくて、自分の置かれた状況をうまく理解できない「その犬」が、ふと振り返り哀しい目をこちらに向けているのが、絵本『アンジュール』の表紙だ。
ところが、『グレイがまってるから』に登場する一匹のシベリアン・ハスキー犬「グレイ」をスケッチする(日本のガブリエル・バンサンとでも呼びたくなる)この 画家の絵はぜんぜん違うんですね。この犬は何を考えているんだか何も考えていないんだか、いつでも「のほほん」としていて、われわれ読者も知らずと心が和んでしまうんです(^^; どうも、あまり頭よくなさそうだし、紫外線アレルギーやら、てんかん発作やら、世間一般の飼い犬の数十倍も飼い主一家に心配を懸けながら、でも、そこにいるだけで皆に愛されている不思議な犬「グレイ」。
世間では「この本」のことを「究極の犬本」と呼んでいるらしいのですが、まさになるほど!納得の本でしたよ(^^)
先ほどから読み始めた、この本の続編『気分はおすわりの日』 伊勢英子(中公文庫)p75 には、こんなことが書いてある。
グレイはそこにいるだけで人の心を平和にするらしい。道の向こうの知らない人も一人の絵描きをも。
矢野顕子の名曲「ラーメンたべたい」じゃないけれど、この本を読んでいると、なんだか無性に犬を飼ってみたくなるのでした(^^;;
小児科医の文章のセンス 2003/08/19
●精神科の医者の中には、文章が巧い人が多いです。古くは、加賀乙彦、なだいなだ、北山修、帚木蓬生。若手では、香山リカ 、春日武彦、山登敬之、斎藤環、などなど。
でも、精神科とどことなく雰囲気は似通っている(?)小児科にも、じつは文章が上手い医者がいっぱいいるのです。先日取り上げた、聖路加国際病院の細谷亮太先生はもとより、岩波書店の『育児の百科』の著者で、結核の専門家で、しかも、マルクス研究家としても名高い松田道雄先生も小児科医です。そして、同じ小児科医仲間からは評判がすこぶる悪い、毛利子来先生は、悔しいけど文章は巧いし、何よりも説得力がある文章を書く。個人的には、飾らない正直な文章を書く山田真先生の文章が好きなのだけれど、1960年代末の東大紛争の頃の山田先生を知っている人の中には、いろいろ言う人もまだいるみたい。
それから、世間ではあまり知られていないけれど『小児科医のアフタヌーンコール』 (北國新聞社)の著者、石川県小松市民病院小児科部長上野良樹先生も、じつに上手い文章を書きます。彼の実のお姉さんが上野千鶴子さんといって、東大で毎日喧嘩を売っている教授であることは、一部では有名です(^^;;
小児科医のウェブサイトは、山のようにあるけど、毎日「日記」をアップしているサイトはほとんどありません。だって、みんな忙しさにかまけて「日記」なんて面倒くさくて書いていられない、そう思っているからです。でも、それを真面目に続けているサイトがあるのです。しかも、そのサイトを運営している先生の文章のセンスが、すこぶる良い!
それは『かたおか小児科クリニック』の診療日誌です。さりげなく書いてあるようでいて、しっかり読ませる。しかも面白くって、ためにもなる。こういう文章は、なかなか書けません。
『かたおか小児科クリニック』 のサイトは、 ぼくがいま一番楽しみにしている小児科医院のサイトです。
お盆休みです 2003/08/13
●8月10日に書いた、聖路加国際病院・小児科部長の細谷亮太先生の山形の実家の菩提寺は、臨済宗ではなくて曹洞宗でした。すみません、訂正いたします。
●本日午後から日曜日まで、北原こどもクリニックは「お盆休み」です。ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。このサイトの更新作業も、日曜日まではお休みです。スミマセン(^^;) 日曜日以降も、8月末から9月いっぱいは何かと仕事が立て込んでおりまして、思うように更新ができないかもしれません。どうかお許しくださいね。
『医師としてできることできなかったこと』細谷亮太 2003/08/10
●『医師としてできることできなかったこと 川の見える病院から』 細谷亮太・著(講談社+α文庫) 読了。
この本は、1995年に出た『川の見える病院から -- がんとたたかう子どもたち』細谷亮太・著(岩崎書店)を文庫化したものです。俳人としても知られる聖路加国際病院・小児科部長の細谷先生は、比較的あっさりとした、淡々とした文章を書かれますが、そのさりげない一文に、読者は逆に引きつけられてしまうようです。ぼくもそうでした。
ただ、読み進むうちに 例えば「こんな文章」に出会うと、ぼくは堪らなくなって、そのページを「ぱたん」と閉じ、目を瞑ってしまいます。
つい最近、その会で容子ちゃんのお母さんから、「寝たふりをしていろんな人をためしたけど、容子の先生がいちばん長くそばにいてくれた」と、彼女が言っていたことを聞きました。
人生で、
----あんなことをしなければ良かったな----
ということはたくさんあります。でも、
----あのとき、ああして本当に良かったな----
と思えることなんて、めったにありません。鼻の奥がツーンと熱くなりました。(p18)
目をつむると、信州大学医学部付属病院小児科で、血液班だったぼくが主治医を務めた子どもたちの顔が、入れ替わり立ち替わり次々に浮かんできます。ぼくは、あの子らに最後まで辛い思いばかりさせて、とても細谷亮太先生のように優しく子どもに寄り添うことがなかった。
そんな悔やんでも悔やみきれない思いで、読み進められなくなってしまうのでした。
でも、ぼくの瞼の裏側に浮かんでくる、今は亡き、Nちゃんや、Hさん、Rくんに、Iくん。長い入院生活の中では、辛いことがほとんどだったはずなのに、ぼくが今、思い浮かべる彼女たち・彼らの顔はというと、何故か皆、笑顔なんです。不思議だな。もしかして、許してくれているのかな。でもそれは、自分勝手な思いこみですね(^^;;)
●ぼくはてっきり、細谷亮太先生はクリスチャンなのだとばかり思っていたのですが、そうじゃなかったのですね。曹洞宗の仏教徒なんですって。そうでなきゃ、四国八十八カ所を、歩き遍路で廻ろうなどとは、思いもつかないはずです。細谷先生が取れた勤続30周年のご褒美特別休暇は、たったの10日間。四国を「時計」に見立てると、ちょうど3時の徳島から、6時の方角の高知まで、一日に30〜40km 歩きに歩いて、四国を4分の1周、お遍路で廻ったのだそうです。それは、今年の3月のこと。
この四国お遍路の旅は、この文庫版書き下ろし「番外編」として、巻末に収録されています。これは面白かった(^^)
●細谷亮太先生の文庫本では、『小児病棟の四季』(岩波現代文庫) もいいですね。最近、さかんに「絵本」に関して発言している柳田邦男さんは、必ず『わすれられないおくりもの』 を取り上げて、この本にまつわる細谷亮太先生と脳症で死にゆく弟を見つめる兄と姉の話をするのですが、そのオリジナルは、この本の最初に登場する「りょうた君」(p3〜13)です。
『編集会議』8月号の「特集:絵本に恋して」 2003/08/06
●昨日、<お父さんにとっての「絵本」とは何か考える>(その6) の中で、『編集会議(8月号)』の「絵本特集」のことを少し書いたのですが、目にする人は、たぶんあまりいないだろうから、こちらの日記に続きを書くことにしました。スミマセン(^^;
●特集の全体を俯瞰して感じたことは、編集者の絵本観がやや古臭くてオーソドックスすぎ、斬新な切り口が見られなかったかな、ということです。これはちょっと残念でしたが、いくつか興味深い発見もありました。たとえば、吉祥寺の絵本専門店「トムズボックス」の店主にして『ダーナ』『ユックリとジョジョニ』『海の夏』『サルビルサ』など数々の傑作絵本を輩出したあの「イメージの森シリーズ」の編集者でもある土井章史さんへのインタビュー記事。(p46)
(彼が主宰する新人絵本作家・養成塾の中で) よく「絵本が好きなんです」という人がいるけど、怪しいねー。じゃあどの作家が好きなのって聞くと、ぜんぜん知らなかったり。そういう人はきっと、絵本という”イメージ”が好きなんでしょう。
<本当に絵本が好きなのか>、<絵本とはどういうものか>、<どうして子どもが面白がるのか>、それをある程度わかるまでに、一年くらいは当然かかると思ったほうがいい。
最近、大人向けメッセージにイラストをつけたような絵本が多いけど、それはあまり好きじゃない。絵本の理想的な読者はいつだって子ども。物語の世界にガッと入っていけるんだから。絵本と関わるには、子どもの気分を呼び起こすことがとても重要だと思う」
子どもの気分を呼び起こす。そのために心がけることはあるだろうか。
「たくさん読んで、絵本のリズムを身体で覚えること。頭で読むんじゃない。いい絵本には、身体が喜ぶリズムがあるから。それは難しいことじゃなくて、たとえば声に出して読むのもひとつの方法でしょう。僕もできるだけ声に出して読むようにしています」
●それから面白かったのは、絵本編集者座談会(p62〜67)。
この中で、偕成社の千葉さんが『ごめんなさい』中川ひろたか・文、長新太・絵(偕成社)の話をしていて、初版では、携帯電話だけ、ちゃんと謝っていないことが、とある子どもの指摘で発覚したんですって。この絵本、たしか家にあったよなぁ、と探してみたら「初版」がありました。確かに携帯電話は「ごめんなさい」をしていない! ぜんぜん気づきませんでしたよ(^^;)
やっぱり、絵本って面白いな、そう再確認できた座談会でした。
清水義範『行儀よくしろ。』ふたたび 2003/08/04
●このところずっと、家庭教育の重要性と可能性について考えているのです。で、再び『行儀よくしろ。』清水義範(ちくま新書)のはなし。うちのサイトの読者に、学校の先生がもしいたならゴメンナサイ。今日はちょっと気分を害するかもしれない。でもこれは、ぼくの言葉じゃなくって、清水義範さんの言葉なんですからね、そこんところ、宜しくお願いいたします(^^;)
「この本」を読んで、最も説得力があった箇所は、「第2章:教育は学校だけのものではない」p51の「先生に期待しすぎるな」の項でした。愛知教育大学出身で、同級生が先生だらけの清水義範さんは、こう言っています。
学校に過大な期待を持たないほうがいい。そして、学校の先生についても、あんまり期待してもなあ、と私は思っている。(中略)
私から見て、ほとんどの先生は、危機感のない公務員で、誇りだけはやけに強く持っているが、社会常識には少し欠けるところがあり、でもとりあえず小・中学生に、教科書の内容を教えることだけは、経験を積んでいるからできる人たちだ。先生なんて、そのぐらいのものである。それで十分に合格である。(中略)
私の知る限りでは、教師は非常に誇りが高い。教師というだけで、世間一般の人間よりも一段上だと思っているんじゃないか、という気がするぐらいである。(中略)
そして、教師という仕事では、主に自分のクラスの子供と接していればいいのであって、同僚とはあまり深くかかわりあわない。上司や先輩の目もあまり気にしなくてよい。教頭や校長というのもいるにはいるが、その機嫌をとらなくても左遷される心配はあまりない。つまり、職場に自分より偉い人間はいないも同然なのである。
世間の、サラリーマン、事業主、商店主、公務員などの、いわゆる普通の大人とのつきあいはほとんどない。教師が多少交流するのは子供のお母さんだけであり、それも上の立場からである。
だから非常に世間知らずで、悪く言えば大人としての常識がなく、なのに職業への誇りだけはゆるぎなくあるのだ。
●ぼくは、この部分を読みながら、思わず笑ってしまいました。だって、この「教師」の部分を「小児科医」に変えても、そのまま文章は正しく成り立つからです。そう言えば、地元の銀行員になった中学の同級生が、こう言ってましたっけ。「顧客で一番気を使って、わがままで手を焼くのは、医者と教師。」だと(^^;;)
世間では、前近代的なギルド集団「日本医師会」に嫌気がさしているのと同様、学校という閉鎖社会に対しても、いい加減にしてよ! っていう気持ちは、誰もがみな持っているんでしょうね。でも、一言いわせてもらえば、医者もサービス業であり、近頃の開業ラッシュの中では、それなりに生き延びる努力をしていかないとヤバイという危機感は持っている。自分の身体ひとつだけが資本のリスクを抱えた自営業の事業主なのですから。でも、先生は違うでしょ。特別優遇された年金で、老後もしっかり保障されたサラリーマンなんだから。
「市民まつり」の夜 2003/08/02
●今日は「伊那まつり」。夕方、徒歩で天竜川を渡って、会場の通り町まで家族4人で「てくてく」歩いて1キロ半。まずは腹ごしらえということになり、向かったのは中華料理店『美華』。大人はラーメン、子どもは硬焼きそばを注文。それから、焼き餃子を2人分と、おとうさんはキリン生ビールの「中ジョッキ」を1杯(^^;)
個人的には、もう少し「硬ゆで麺」が好きなのだけれど、あっさり系スープと、中華三味のノンフライ麺のような感じの麺とのバランスが絶妙な、ここ『美華』のラーメンが、じつは本当は、ぼくの一番好きなラーメンだったのだな(^^) 最近「こってり系」に浮気していてゴメンナサイね。
「市民おどり 」を、通りの歩道から、ただ眺めているだけというのは、案外退屈なものです。
夜9時を過ぎて、田んぼ道を家路につきながら、小1の長男が言いました「今日は、あんまり面白くなかったな。」「そりゃそうさ!」ぼくは答えました。「お祭りってのはね、ただ見てるだけじゃ、つまらないんだ。踊る側になって、みんなから見られなきゃ。ね!」
天竜川を再び渡る前には、次男は歩けなくなって、あとはずっと、お父さんがおんぶ。家に帰り着き、ふと自宅前の田んぼの用水路を見やると、ホタルが1匹。草むらの影で、ひとり一生懸命、点滅していました。あ、そうか。夏が来たんだね、ようやく(^^)
<先月の日記>へ
●
|
T O P |
ご案内 |
おとうさんの絵本 |
読書&CD |
Now & Then
|
リンク |
|
北原こどもクリニック
|