| しろくま 不定期日記 | |||||||||
|
2002年:<10/11月> <12/1月> 2003年:<2/3月> <4/5月> <6/7月> <8/9/10月><11/12月> 2004年:<1/2/3+4月><4 / 5/6月>< 7/ 8/ 9月> < 10/ 11月> 2005年:< 12月/ 1月> |
「八ヶ岳小さな絵本美術館」アンソニー・ブラウン絵本原画展 2005/03/21
●昨日、日曜日の続きのはなし。午後2時からは、原村の「八ヶ岳自然文化園」で、絵本作家アンソニー・ブラウンの講演会。倉科パパとも合流。大人のための講演会だったが、うちの子供たちも入れてもらって聴講。でもやっぱり30分もたなくて、妻は2人を連れて途中退場し、自然文化園の世界のカブトムシ・クワガタムシ展とプラネタリウムへ。
英語の聞き取りはぜんぜんダメだったが(^^;;) フェリス女学院文学部教授の藤本朝巳先生が、解説も加えて逐一丁寧に日本語訳をつけて下さったので、アンソニー・ブラウンの絵本製作の秘密や、彼がどうしてあんなにもゴリラが好きなのかよーく解って、とっても面白かった。しかも、プロジェクターで80枚以上のスライドを使って、子供の頃に描いたイタズラ書きに始まって、美術大学時代の習作、医学解剖図譜、彼が手がけた絵本の数々を次々と映し出しながら説明してくれたのだ。
興味深かったのは、テキストではなくて「絵に語らせる」ことの訓練を、絵本作家になる以前に、マンチェスター王立病院で、手術所見の図譜や解剖図譜を描く専門画家として働いていたときに、身につけることができた、そう彼が語っていたことだ。実際、手術所見は写真が最も正確には違いないのだが、写真だと、重要ではない余計なものも同等に写ってしまい、見ても案外よく分からないのだ。それを、専門画家がすっきりと整理して、でも正確に描くことで、見る者の理解は一気にすすむ。そういうことは確かにあるな。大切なことは「絵に語らせる」アンソニー・ブラウンの原点は、こんなところにあったのか。
●講演会のあと、サイン会があって(持参した『どうぶつえん』と『すきですゴリラ』にサインしてもらえたよ(^^)、今度は「八ヶ岳小さな絵本美術館」に皆で移動して、なんとアンソニー・ブラウン自身が『すきですゴリラ』を読み聞かせしてくれたのだ。ぼくも大好きな絵本だし、これは感動的だったな。息子たちも最前列に陣取って聞かせてもらった。彼が英語でテキストを読んで、その間、藤本先生がもう一冊同じ絵本を広げてみんなに見せる。藤本先生が日本語で文章を読んでいる時は、今度はアンソニー・ブラウンがぼくらに絵本を広げて見せる。そんな感じでの読み聞かせだった。
驚いたことに、アンソニー・ブラウンが読んでいた『すきですゴリラ』は、原書ではなくて日本語版。彼は英語のテキストを暗唱していたんだね。すばらしく素敵な時間が流れたのだった。
■アンソニー・ブラウン絵本原画展のはなしは次回また書くことにするが、とにかくこれは凄い! 一見の価値大いにありです。5月連休明けの、5月9日(月)まで、「八ヶ岳小さな絵本美術館」で開催中。ぜひ見に行ってください。
大泉「絵本の樹美術館」から、原村「八ヶ岳小さな絵本美術館」へ 2005/03/20
●暖かだった土曜日とはうって変わって、冬に舞い戻ったかのような寒い底冷えのする日曜日だった。今日は、「細密な絵本原画を見るツアー」の一日を、父さんは計画したのだ。中央道・長坂インターで下りて、八ヶ岳に向かってずんずんのぼって行き、甲斐大泉駅の横、小海線の上を越える陸橋を渡らずに、その手前で右折します。すぐに、ソフトクリームの看板があるので、そこをもう一度右折。少し西へ下ると、左手に不思議な家屋が見えてきます。
ちょっと派手な作りのログハウスで、去年までは、煙突から侵入しようとするサンタクロースが一番目立っていたのだけれど、何と!この春には、家屋の西側にツリー・ハウスが完成し、その木の枝には、スパイダーマンがしがみついているのでした(^^;) いやぁ、たまげましたよ。この家は、何も営業をしている訳ではないごく普通の家なのです。信じられないよね。連日、勘違いした観光客が自宅へ迷い込むんだそうです。そりゃ、そうだ!
でも、ここが「絵本の樹美術館」ではありません。もう 25m ほど下って、今度は左折すると、2軒目にあるのが「絵本の樹美術館」なのです。冬季休業を終えて、昨日オープンしたばかりでした。1Fでは斎藤隆夫さんの『かえるの平家ものがたり』原画展が開催されていましたよ。絵本になった絵と、ほぼ原寸大の原画は、それはもう素晴らしいものでした。じつに細かく細部まで「これでもか!」っていう感じで、作者の斉藤さんは絵を書き込んでいるのです。
妻は「はぁ…」とため息ををつきながら、ふとこう言いました。「荒井良二さんが、ささっと書いた絵が、スウェーデンで認められて、3000万円になったんでしょう? 長新太さんも、いとうひろしさんも、描いてすぐ本になってるのに、斎藤隆夫さんは、こんなにも一生懸命に時間をかけて、細かく細かく書き込んで、ようやくやっと一枚の絵を仕上げているのよ。でも、貧乏なんでしょ! どうしてなの?」
ほんと、そうだよな。世の中、いろいろとうまくいかないね。
ちょいと長居をしすぎて、「絵本の樹美術館」を後にしたのは、12時半をすでにまわっていた。この時間になると、カレーの「アフガン」は2時間待ちだし、石釜焼きピザの店「バックシュトゥーベ」の駐車場も車でいっぱい。しかたなく、鉢巻き道路を小淵沢へもどって、カレー専門店「クロ」へ。うちの次男が、どうしても「カレーが食べたい!」そう言ったからだ。ログハウスなのに、こてこてした店で、店内には大きな水槽がたくさん並んでいる。スパイシーなカレーは美味かったけれど、ちょっと不思議すぎる店だったな(^^;; (つづく)
アンソニー・ブラウン 来日講演会(八ヶ岳小さな絵本美術館) 2005/03/17
●現代イギリスを代表する絵本作家で、ぼくも大好きなアンソニー・ブラウン氏(この、翻訳家灰島かりさんの解説はスルドイな)が、再び来日する。
来る3月20日(日)には「八ヶ岳小さな絵本美術館」主催の「アンソニー・ブラウン講演会」が、八ヶ岳自然文化園で午後2時から開かれる。世界の絵本・昔話研究家の藤本朝巳先生が通訳してくれるそうだ。
ぼくらは、家族全員で聴きに行く予定。シェイプ・ゲームとか、ワークショップみたいなものも、やってくれないかなぁ(^^)
『私のカントリー』春号(主婦と生活社) 2005/03/16
●昨日発売の季刊誌、『私のカントリー No.52』春号 (主婦と生活社 \1350+税) では、「絵本を開いて心の旅へ」という特集を組んでいて、河合隼雄さんと落合恵子さんの絵本対談とともに、気になるあの人のマイ・フェイバリット絵本として、10人の「絵本と係わる人たち」が、それぞれ「私のベスト3」を紹介している。その97ページに、何と!このぼくが載っているのだ! しかも、あのケロポンズと松田素子さん(ぼくがすっごく尊敬する絵本編集者)にはさまれて…… 光栄の至りだけれど、身分不相応な待遇に恐縮するばかりだ。
昨年の12月中旬、突然メールがあって、今度『私のカントリー』で「絵本特集」をするので、絵本識者(絵本作家・絵本専門店店主・絵本編集者など)10人に、お気に入りの絵本3冊を挙げてもらう企画で、このぼくにも、日頃こどもと係わる小児科医の立場から、是非参加して欲しい、という内容だった。
最初は、絵本素人のぼくには無理です。そう、おことわりしようと思ったが、このせっかくの機会を逃すのは、ものすごくもったいないことかもしれない、そう、ふと感じられて、引き受けることにしたのだった。
ただ、問題はあった。これは、先日の名古屋でも指摘されたことだが、ぼく自身が大好きな絵本は、あくまで「ぼくが好きな絵本」なのであって、それを自分の子供たちに読み聞かせしたことはないし、伊那のパパ's でやっている「絵本ライヴ」で、たくさんの子供たちを前に読んでみようと、思ったことは一度もない。矛盾しているようだけど……
例えば『オレゴンの旅』。それから、『ナヌークの贈りもの』に、ガブリエル・バンサンの『ナビル』。そうして、『クレーン男』に、『島ひきおに』。みな、ぼくの大切な絵本なのだが、自分の子供たちにも、他人の子供たちにも、これらの絵本を読んだことはまだ1回もないし、当院の待合室の本棚には(本が傷むのが悲しいから)置いてない。小さな子供向きの絵本ではないしね。
『やまあらしぼうやのクリスマス』だけは、おかあさん方には何度も読んでいるけども。
こういう、ごく個人的な愛好の書を、大々的にオススメしちゃっていいのかなぁ、という戸惑いはあるのだった。
●写真の中で、ぼくが抱えているのは「こん」 のぬいぐるみ。『母の友』(福音館書店)の付録になった「こん」の型紙から、妻が作ってくれたものだ。ありがとね(^^;)
「ヒロシです」 Part 2 2005/03/13
●昨日の土曜日の午後は、天使幼稚園で「パパ's 絵本ライヴ」。今回で通算9回目だ。5人のメンバーのうち、坂本パパが欠席だったので、4人のパパでそれぞれ2冊づつ読んだ。今回の注目は、宮脇パパのギター・デビュー。いやぁ、よかったっすよ! 「すっぽんぽんのすけ」の歌(^^)。
ライブの詳細は、後日ご報告いたしますが、会の終了後には、それぞれのファミリー全員そろっての「おつかれさま・打ち上げ会」を、「いなっせ」を西へ少し行ったところの、もんじゃ焼き「佐榮」で盛大に執り行った。その場で、お花見、流しソーメン会、キャンプ等、夏までの年間行事が決定したのだった。楽しみだな(^^)
●今日の日曜日は休日当番医だった。まだまだインフルエンザは流行しているので、ものすごく忙しかった。トータル、116人の患者さんがやって来た。そのほとんどがインフルエンザ。はぁ、疲れましたよ。午前の部が、13:49 で終了して、あわてて昼飯の「ちむらのちらし寿司」を口の中へかけ込み、午後2時からは午後の部が始まった。美味しいお鮨も、ゆっくりと味わっている間がないのだ、残念!!
■午後6時前に、ようやく診療を終えて、夕食を食べていると、うちの息子たちのエンタテイメント・タイムが始まった!
とにかく、最近の「お笑いブーム」に便乗して、「エンタの神様」とか、毎週うちの「HDレコーダー」に録画されているので、子供たちはリモコンを駆使して繰り返し繰り返し見てるのね(^^;) だから、やたら詳しいんだ、お笑い。お父さんが知らないコンビの名前をよーく知っている。
でも、このCDが流れると、うちの次男は突如、ズボンのポケットに右手を突っ込んで、「ヒロシ」になりきるとでデス。あはは(^^)
「○○です。かけ算は、九九で言えるのに、足し算ができません……。指が足りないとです!」
あはははははは(^^;;;;;
3月はなんだかいろいろと忙(せわ)しない 2005/03/11
●次男が通う天使幼稚園でも、インフルエンザが蔓延している。うちの子も、先週末ぼくが名古屋に行っている時に、39.8℃の熱を出した。B型インフルエンザだった。
昨日の午後には、同じく年長組の宮本侑季ちゃんが熱をだして外来にやって来た。
「せんせい! わたし、インフル・レンジャーにやられちゃったみたい……」
あはは(^^) ホントかわいい「言いまつがい」でしたよ。
●ここの「かたおか小児科」ココログを読むと、レンジャーものの変遷が詳しく述べられていて面白い。それにしても、片岡先生はよく知ってるねえ。絵本に熱い思いを寄せる小児科医が、全国各地から名古屋に集結した! 2005/03/08
●今年の8月に、医歯薬出版社から出版予定の『小児科医が見つけた えほん・えほん・絵本』(仮題)の編集会議が、この土日に、名古屋の「メルヘンハウス」の2階で開かれた。 名古屋の「佐々木こどもクリニック」の佐々木邦明先生を編集長に、宮城県宮城郡利府町「たかだこども医院」の高田修先生、千葉県松戸市「おのクリニック」の小野元子先生、香川県高松市「住谷小児科医院」の住谷朋人先生、兵庫県西宮市「明和病院」小児科の多田香苗先生、山口県周南市「たにむら小児科」の谷村聡先生、それに、長野県からはこの僕が、編集委員として参加した。
同じく編集委員の、鹿児島県鹿屋市「まつだこどもクリニック」松田幸久先生は、時季はずれの大雪のため飛行機が飛ばず、欠席となり残念。
■それにしても、絵本に熱い思いを寄せる同好の志の小児科医が、全国各地にこんなにもたくさんいるのだ! ということを再確認できて、ぼくは何だかとってもうれしかったです。皆さんから、いっぱいの元気の素をもらって、名古屋から帰ってきましたよ p(^^)q
★「いい本」ができるといいな(^^)
『絵本であそぼ!』パパ's 絵本プロジェクト・著(小学館)発売 2005/03/05
●この3月2日に、『絵本であそぼ!』 パパ's 絵本プロジェクト・著(小学館)が、発刊された。
これは、今までにない画期的な本だと、悔しいけれど正直そう思った(ちょっと、ほめすぎだな(^^;;)。本を読んだ感想の詳細は、来週アップする予定だが、一人でも多くのお父さんに、手にとってほしい本だと思うぞ。
この本に関連して、Google で「パパ's 絵本プロジェクト伊那」と入れて検索したら、なんと、われわれ「伊那のパパ's」のメンバーである「伊東パパのブログ」が引っかかってきましたよ。ぼくらの知らないうちに、ブログなんてオシャレなもの立ち上げちゃって、このこのっ >伊東パパ (^^;なんだか、もの凄く忙しい日々が続くのだ 2005/03/02
●インフルエンザ流行の勢いが止まらない。先週の月曜日、当院開院以来の1日あたり最高来院患者数を記録したばかりだったのに、今週の月曜日(2月28日)には、いとも簡単にその記録は塗り替えられたのだった。午前の診療が、午後1時半を回っても終わらず、予約した4人の患者さんに「お詫び」の電話をして午後の診療に回っていただき、つばめタクシーで急いで保健センターへ。すっかり忘れていたのだが、この日は3歳児健診の日だったのだ。
トータル26人だったから、比較的少なくてよかったな。何とか午後3時前には健診を終わらせて、10分遅れで午後の診療開始。午後の予約も目一杯入っている。こうなると、高熱の患者さんをいちいちインフルエンザ迅速診断検査していたのでは、診療がいつまで経っても終わらない。あとは臨床所見のみで勝負するしかない。
その子の顔の表情を見て、その子が通っている保育園の名前を聞けば、たいていは直ちに判断できるのだが、この段階では決してインフルエンザですねと断言しない。聴診器を当てて、おなかを触診し、最後にのどを見て、はぁ、う〜む、これは…… なるほどねぇ。という顔(すなわち、これはインフルエンザの喉の所見が出ている、という意味)をしてから、おかあさんの顔を見るのです。
それから一呼吸おいて、おもむろに、おごそかに「インフルエンザですねぇ、しかも、B型だ! おかあさん」そう言うのです。たいていの母親は、その一言で「ははぁ〜、わかりました。タミフルを処方してください。」と、納得するはずだ。重要なことは、医療というのは「医者と患者の契約関係」で成り立っているということだ。すなわち、お互いの利害が一致すればそれで、よいのです。
●世の中のお母さん方には、インフルエンザの迅速診断検査をして陽性に出ないと、タミフル(インフルエンザの薬)は処方してもらえらいと思っている人が多いのですが、決してそんなことはありません。臨床所見のみで、医者がインフルエンザと診断して処方して一向に構わないのだ。
だから、検査をしないで「インフルエンザB型です。おかあさん!」そのように当院で言われた場合には、どうか素直に信じてくださいね(^^;) そうして、ようやく午後7時半過ぎに外来の診療が終了した。はぁ、疲れたよ、ホント。 その後に「テルメ」 へ行って、帰宅後は2月のレセプトの点検を、深夜まで。
●そうして、今日の午後2時〜3時まで、校医をしている伊那東小学校の6年生対象に、「薬物乱用防止のために」というタイトルで、授業をしてきましたよ。水谷修「夜回り先生」の講演を参考にして、今回は、去年よりは上手な授業ができたかな。よし(^^)。 もすこし、がんばれ!ふたたび「みしま」のラーメンについて 2005/02/25
●鶴瓶のはなしは、次回にして(このところ忙しくて、パワーが残ってないんです)、ふたたび「みしま」のラーメンについて。
先日、外来診療をしながらふと、何だか急に、どうしてもラーメンが食いたくなって、夕方、妻子の前で「今日はラーメンを食いに行くぞ!」そう宣言した。すると、小学2年生の長男は「二八のラーメンがいい!」といい、妻は「みしま!」と言った。ちなみに、次男(6歳)は「権兵衛で肉が食いたい!」と、頑なに主張した(^^;)
決定権は、家長であるぼくにある。「よし、今日は、みしま!」ということになった。伊那市駅前を南に線路沿いの狭い道路を車で抜けると、左手に「ちむら」の看板。肉をあきらめた次男は、変わり身も早く、大きな声で「ちむらのすしが食べたい!」そう叫んだのだが、父さんは冷たく却下して、田中病院を通り過ぎ、左折して線路を越え、「倉科洋品店」の向こう、少し行った左手の駐車場に車を停めた。
ガラス戸を開けると、ラッキーにもテーブル席は空いていた。「寒いねぇ〜」と席につくと、カウンターの常連さんの視線を感じる。われわれ家族はこの店の雰囲気に不釣り合いなので、常連さんからは奇異で興味本位に見られてしまうのだな。一杯のラーメンを親子で分け合いながら背中をまるめて「おいしいねぇ」と食べる姿を横目で見ながら、「一杯のかけそば」親子のように不憫に感じるのであろう。
ぼくと妻はラーメンを注文し、長男はチャーハンをたのんだ。肉へのこだわりを捨てきれなかった次男は、豚カツを所望した。この豚カツが美味かったなホント。ぼくは、ラーメンのスープを「ズズッ」とすすりながら、しみじみ「みしまのラーメンは美味いな」そう思った。やっぱり、伊那で一番好きなラーメンだ。ちなみに、二番目に好きなのは「美華」のラーメンで、三番目に好きなのは「麺屋・二八」の塩ラーメンと、「万里・菜館」のラーメンか。中年を過ぎて最近では、やっぱり「こってり系」よりも「あっさり系」が好みなのだな。
あと、「みしま」はやっぱり、その佇まいがいいのだ。清潔だけど、決して気取っているわけではない。世の中にくたびれてしまった、落ちこぼれた人々を、そっとやさしく包み込む包容力がある。だから、ぼくら親子もこの空間の中では許されてしまうのだな。そこがウレシイのかもしれないね(^^;)
笑福亭鶴瓶の、ちょっといい話(ふたたび) 2005/02/22
●今日も、落語に関するはなし。落語はホント面白いのだが、TVメディアやネット上では超マイナー扱いが続いている。変に通ぶった人とか、生き字引であるところの小林信彦さんのようなご意見番が目を光らせているので、下手なこと言えないんだな。あの、糸井重里さんでさえ、落語を語るときには、ずいぶんと気を使うらしい。
でも、彼のこんな発言 とか読むと、けっこう本音が聞けてるようで、すごく面白い(^^)
●最近では、もっと若い人も落語に注目しているようだ。「週刊文春」連載中の「ホリイのずんずん調査」でも、最近になって堀井さんも熱烈な落語ファンであることが判った。そーかそーか、そーだったんだね(^^;) うれしいぞ!
■昨年の12月から、神奈川の三浦半島の先端にある、マグロ漁港の三崎を引っ越して、トナカイの大きな縫いぐるみを所有する奥さん(『絵描きの植田さん』に登場する女性のモデルか?)と、現在は長野県松本市里山辺の山のほうに住んでいるらしい、いしいしんじさんの「ごはん日記」12月4日とか読んでると、いしいしんじさんも、落語好きであることがよく分かる。いしいさんは、上野に住んでいた頃に柳家小三治の独演会には昔からよく行っていたようだ。もともと大阪出身の人なので、本来は上方落語のはずだが。
となると、六代目・笑福亭松鶴だわな(^^)
最近、この六代目・笑福亭松鶴をモデルにしたミステリー小説が評判を呼んでいる。タイトルは、『笑酔亭梅寿謎解噺』田中啓文・著(集英社)定価: 1,890円(税込)。
田中啓文氏は、最近ハヤカワ文庫で出版された『蹴りたい田中』が一部で話題となった、駄洒落好き!かつ、ファラオ・サンダース好き!かつ、フリー・ジャズ好き!かつ、上方落語好き!を自認するSF・ミステリー・ホラー作家だ(^^;)
その田中啓文氏が、新作『笑酔亭梅寿謎解噺』を出版する時に、印刷されたばかりの著書を抱えて、六代目・笑福亭松鶴のお墓にお参りに行ったんだそうだ。そしたら、なむなむ、と拝む田中氏の背後で、突如ひとの気配がした! ビックリして振り返ると、笑福亭鶴瓶さんが「そこ」にいたんですって。これ、ホントの話。大森望氏が、上記「小説すばる」の書評で書いているぞ。(つづく)パパ's 絵本ライヴ in 長谷村 PTA 親子文庫 2005/02/20
●昨日の土曜日は、明け方の雪が午後には雨に変わった。思いのほか暖かかったようだ。午後3時半からは、 長谷村公民館 で今年初の 「パパ's 絵本ライヴ」 。11月に「いなっせ」で行った 「上伊那親子文庫」 でのぼくらのライヴを見た、長谷村 PTA 親子文庫代表のおかあさんが「是非に」と呼んでくれたのだ。ありがたいこってす(^^;)
例によって 『はじめまして』 新沢としひこ(すずき出版) を全員で歌って、自己紹介。久しぶりだったので、ちょっと、とちっちゃったよ(^^;;
今回トップバッターは 坂本パパ 。夕方5時には松本に行かなきゃならないので、先頭で登場。読んだ絵本は、 『かえるをのんだととさん』 (福音館書店)。例の岩波書店から出版された、長谷川摂子さんの 「手のひら昔話絵本」シリーズ から最後に出た 『だんだんのみ』 と同じはなしだ。2月だからね、節分と鬼のはなし。この絵本は 斉藤隆夫 さんの絵がじつにいい。困り果てた「ととさん」が頼るのは、やっぱり かかさん なんだな 。でも面倒くさい「かかさん」は、「おしょうさまに訊きなされ〜」。その繰り返しがじつに心地よい(^^)
2番手で登場は、 北原パパ 。今日も子供たちの ウケを狙って BGM付き 『バナナです』 (^^;)
単なる「受け狙い」に走るのはよくないとは思いつつ、伊東パパに「ヒロシです。が受けるのも、今のうちだけですよ!」そう言われて、勇気を出してまた読むことにしました(^^;;
思いのほか、保育園児から小学校高学年の女子にまで、けっこう受けた。後ろのほうで聞いていたおかあさんがたも、暖かい視線を送ってくれていたぞ。あぁ、よかった(^^;) 会が終わってから、小学校6年生ぐらいの利発そうな女の子がぼくのところにやって来て、「あのヒロシですのCD、どこで見つけたんですか?」と訊いてきた。「それはヒミツです。」ぼくは笑って答えた。
■この日のクリンナップは、伊東パパ。読んだ絵本は、エリック・カールの『できるかな? あたまからつまさきまで』(偕成社)。
長谷村の子供たちは、ちょっとおとなしいのかな。体を動かし出すまで、ちょっと時間がかかったぞ。「できたよ できたよ!」でも、伊東パパの動じぬ演出力によって、いつもと変わらぬ盛り上がりを見せてくれましたよ。

つぎは、『いっぽんばしにほんばし』中川ひろたか ・作、相野谷由起・絵(アリス館)です。小学校の高学年ともなると、手遊びなんて恥ずかしくてできないのだけれど、長谷村の小学生はみなつき合ってくれましたよ! うれしかったな(^^)
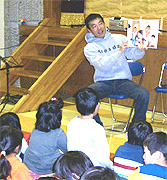
■続いて宮脇パパが登場。この日読んだ絵本は、『うんこ日記』村中李絵・作、川端誠・絵(BL出版) これはスゴイ絵本だねぇ。だって、うんこの絵日記なんだもの。そのリアルさに大人は引いてしまうのだけれど、こどもはうんこが大好きなのさ。ウンコが積み重なるごとに、子供たちの歓声が上がる(^^)
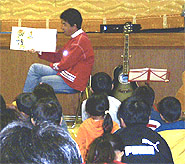
トリは倉科パパ。読んだのは、十八番の『じごくのそうべえ』。「糞尿地獄」が登場して、またまたウンコだったが、やっぱり倉科パパの「そうべえ」は何度聞いてもいいねぇ(^^)
おしまいに『世界じゅうのこどもたちが』をみんなで歌って、無事終了。長谷村の子供たちは、みんな純朴で素直で、いい子ばかりだったな。よかったよかった(^^)
●次のライヴは、3月12日(土)午後3時半〜 「天使幼稚園」にて。
笑福亭鶴瓶の、ちょっといい話 2005/02/19
●つねに数冊の本を同時進行で読んでいて(途中で止めてそれきりの本も多いのだが)ときどき、いま何を読んでいたのか判らなくなることがある。最近読んでいる本は……
『神はサイコロを振らない』 大石英司(中央公論新社) 著者久々のハードカバー本にして、ラブ・ストーリー。なかなか読ませるぞ。面白い。「腰巻き」がよくできているな。本屋さんで平積みされれば、これは売れるか。タイトルもいいね、アインシュタインの言葉みたい。
『恥ずかしい読書』 永江朗(ポプラ社) 永江さんは、ぼくと同い年なんで、ちょっと意識しているのだ。その他に 1958年生まれの同い年文化人に誰がいるかというと、 みうらじゅん 、 坪内祐三 、 山田五郎 、それから 原辰徳 。何だかみんな、マイナーだなぁ(^^;; ちなみに、女子部を見渡すと、 森昌子、桜田淳子 、それから1959年生まれだけど 山口百恵 は早生まれなので同学年なのだった。
『アダムの呪い』 ブライアン・サイクス(ソニー・マガジンズ) 昨年末から読み始めて、もうちょっとで読み終わる。面白いんだけど、最後で失速してしまったかな。
『おあとがよろしいようで』 橘蓮二・写真(講談社文庫) その場の空気まで、写真に記録できるんだな。芸人が楽屋でしか見せない 素の表情 を、この写真集で垣間見ることができる。鬼籍に入ってしまった噺家も多数収録されていて、特に 志ん朝さん が何ともいえない粋で鯔背な所作を見せているのが貴重だな。一度「生で」見たかった。
『魔法』 クリストファー・プリースト(ハヤカワ文庫) 単行本で読んだとき、ビックリしたこと以外は内容をすっかり忘れてしまったので、もう一度読んでみることにしました(^^;
『あなたの人生の物語』 テッド・チャン(ハヤカワ文庫) この人はスゴイね! ほんと凄い。SFの未来は明るいぞ! 感想はまた、いずれ。
『小沢昭一がめぐる 寄席の世界』 小沢昭一(朝日新聞社) 小沢昭一が、落語を巡って12人と対談するのだが、この本は勉強になる。 桂米朝との対談に始まって、笑福亭鶴瓶、立川談志を経て、矢野誠一で終わる。どの対談も読み応えがあるが、特に、 笑福亭鶴瓶 との対談がいい。その詳細は次回に。
高田渡 Live at the Jazz Cafe "Base"(その3) 2005/02/17
●昨日は「いずみ」で伊那市医師会の新年会。「順調に痩せてきたんだって?」とT先生に言われ、S先生は「見た目あまり変わらないねぇ」と、ぼくの顔をまじまじと見ながら言った。しまったなあ、へたなこと書くんじゃぁなかったよ。ダイエットはホントむずかしい。
二次会へと向かうマイクロバスには乗らず、歩いて「いなっせ」まで行き、閉店まぎわの西澤書店で子供に頼まれていた『コロコロコミック3月号』を購入。さらに歩いて天竜川を渡ると、右手に 「Jazz Cafe "Base"」 。ちょいと寄り道して店の中へ。
■ここのマスターは、以前駒ヶ根で 「Kanoya」 という店をやっていた。ぼくは行ったことなかったが、頻繁に東京から有名なジャズメンを呼んで店でライヴを打つことで地元では有名な店だった。で、伊那の新しい店でも「ライヴ」をやろうじゃないか! ということになったらしい。しかし、「Jazz Cafe "Base"」は、カウンターと丸テーブル3つだけ(あとは、大きなスピーカーが2つ「でん」とある)の、とっても小さな店で、ライヴを打てるようなスペースはどこにもない。
本当にこの狭いスペースで 高田渡 のライヴができるのか? ずいぶん心配したのだが、当日はなんと30人近くの客が入った。ぼくはカウンター右端の最後列の席だったけど、それでも歌っている高田渡さんから 3m も離れてはいなかったよ。客層はというと、ぼくと同年代のオジサン・オバサンが多かったかな。
そこへ、リンカーン大統領みたいな顎髭(まっ白)の高田渡さん登場。アレルギー性鼻炎が急にでたみたいで調子悪そうだったけれど、知ってる唄をいっぱい歌ってくれてうれしかったな。最初は「乗るんだよ、電車によぉ〜」と始まる 「仕事探し」 。それから「コーヒーブルース」「鎮静剤」「値上げ」「失業手当」「アイスクリーム」「あきらめ節」「夕暮れ」「鉱夫の祈り」「魚釣りブルース」「ブラザー軒」、そしてぼくの大好きな 「生活の柄」 。
途中、休憩をはさんで夜の9時半過ぎまでライヴは続いた。しみじみ、ほのぼのよかったよ。マスターに訊いたら、その後の打ち上げでは午前3時まで盛り上がり、高田渡さんもずいぶんとご機嫌だったらしい。翌日は、マスターが渡さんを連れて高遠の 「壱刻」 へ蕎麦を食べに行き、次のライヴ会場の松本へ向かったそうだ。それにしても、厳寒のこの時期に、わざわざ信州をライヴ・ツアーすることはないんじゃないかなぁ。フォークシンガーも大変だね。
高田渡さんのドキュメンタリー映画 『タカダワタル的』 が昨年ずいぶんと評判を呼んで、最近は若い人からも注目されているらしい。お酒、あんまり飲み過ぎないで、いつまでも元気で唄い続けてほしいな。(おわり)
高田渡 Live at the Jazz Cafe "Base"(その2) 2005/02/14
●あの頃のフォークの人たちって、今もぜんぜん変わらない。メジャーを維持している吉田拓郎とか井上陽水とかは別だけど、ギター1本さらしに巻いて(^^;) 北は北海道から南は九州、沖縄まで、マネージャー同伴ではなくたった一人で、小さな町のライヴハウスを今日も巡っているのだ。
加川良 さんは、富士見にいた頃の1995年4月8日、茅野市宮川・諏訪大社上社前の 居酒屋「ジョン・ノレン」 で聴いた。ライヴで見たのは、1972年の長野市民会館以来だったが、髪の毛が短くなった以外ぜんぜん変わってなかった。良さんは若々しかったのだ。正直驚いた。
友部正人 さんのライヴは、たぶん一番多く聴きに行っている。筑波アクアク、東京では 中川五郎 さんとのジョイント、長野でも聴いたし、松本松竹劇場の閉館記念での 「たま」 とのジョイント・ライヴも聴きに行った。友部さんもぜんぜん変わらないね。いつまでも少年みたいだ。 中川イサト さんも、10数年前に飯山公民館で聴いた。 小室等 さんも同じ頃に飯山のお寺の本堂でのライヴを聴いた。みな、地道に地味に、活動を続けていたのだ。
ただ、 高田渡 さんだけは、一度もライヴを聴きに行ったことがなかった。何故か不思議と、今までまったくそのチャンスがなかったのだ。初めてラジオで彼の唄を聴いて33年経ってようやく今回、伊那で 生の高田渡 を体験できた。彼も、ぜんぜん変わっていなかった。ただし、彼は70年代初頭の当時から達観し老成した仙人みたいな風格があったので、既に相当なオジサンだと信じていたのだが、何と彼は1949年生まれで、ぼくより9歳年上なだけだったのだ。えぇ〜信じられない。1960年代後半のデビュー時には、高田渡はまだ高校生だったのだ。
と言うことは、現在55歳か。でも、実年齢よりも20〜30歳は老けて見えたよ。 昔から酒好きの年寄りみたいだった という意味では、高田渡さんも変わらないのかな(^^;)
(も少し、続く)
高田渡 Live at the Jazz Cafe "Base" 2005/02/12
●昨日は、高遠の 「だるま市」 だった。天気は良かったのに、人出はイマイチだったかな。昨年の2月11日もそうだったが、この日も 「兜庵」 へ行って 十割蕎麦 を食べた。そば粉100%とは、とても信じられないくらい滑らかな喉ごし。基本的には黒い田舎蕎麦なのだが、店主の入魂の蕎麦打ちによって、蕎麦が洗練されてくるのだ。ぼくは こういう蕎麦 が好きだな。蕎麦つゆの鰹出汁の利き具合もよい。唯一つ難を言えば、ここではお酒が呑めないことか。あ、それからもう一つ。 そば湯がぬるい! これは決定的にマズイんじゃぁないか?
■夕方伊那へ帰り、一眠りして酔いを醒まし夜7時前には自宅を出る。木枯らし吹き荒ぶ街中を歩いて 「Jazz Cafe "Base" 」 へ。今夜はここで 高田渡 のライヴがあるのだ。 「Jazz Cafe "Base" 」 は、昨年の10月半ば、伊那市立図書館から中央橋を渡って天竜川の東岸にある 「ホテル・センピア」 の対面に突如オープンした 「ジャズ喫茶」 だ。夕方から深夜までやっていて、ジャズ喫茶というよりは ワン・ショット・バー といった雰囲気か。ボトルキープはない。「一杯飲み屋」なのだ。
一杯のみ屋を 出てゆくあんたにその 「彼」 というのが、 高田渡 のことなのだ。
むなしい気持ちが わかるなら
汚れた手のひら 返してみたって
仕方ないことさ
あせって走ることはないよ
待ちつかれて みることさ
ため息ついても 聞こえはしないよ
それが 唄なんだ
僕が歩こうとする道には いつも
彼の影が映ってたみたいです
小さな影でしたが
誰だってその中に入りこめたんです
それから 彼の親父が
酔いどれ詩人だったことを知り
今 僕が こうしてるから
彼こそ 本当の詩人なのだと
言いきれるのです
(加川良 『下宿屋』 より)
●ぼくはこの 加川良の『下宿屋』 を、ラジオの深夜放送で初めて聴いた。たしか中学2年生の時だったから、1972年のことだと思う。当時よく聴いていたのが 東海ラジオ の深夜放送 「ミッドナイト東海」 で、 チェリッシュ 、 森本レオ 、 笑福亭鶴瓶 、 兵藤ゆき がパーソナリティを務めていた。鶴瓶はこの頃(もう少し後からだったかもしれないが)から知っていて、すっかりファンになった僕は、その後の日曜日の深夜に密かに ラジオ大阪 で放送されていた 『鶴瓶・新野の ぬかるみの世界』 も、番組終了までずっと聴いていた。
たぶん初めて聴いたのは、チェリッシュの担当日だったと思う。印象的なギター伴奏に乗せて、歌わずに ただ、とつとつと語る この『下宿屋』を聴いて以来、ぼくは熱烈な加川良のファンになった。ぼくの大好きな加川良の 師匠 が 高田渡 なのだから、当時中学生だった僕には神様みたいなもんだったな、高田渡さんて。
でも、中学生には 「山之口貘」の詩 は難しくて、そのよさを理解できなかった。最近だよ、しみじみその言葉が心に沁み入るようになったのは。(つづく)子供を褒めること(その2) + 高田渡ライヴ 2005/02/11
● 子供を褒めること に関しては、汐見稔幸先生も 『0〜5歳素敵な子育てしませんか』 (旬報社)の中で、こんなことを言っている。
よく「ほめて育てる」と言われていますが、小さな子どもの場合、私はほめすぎることはよくないと考えています。それは、ほめること・しかることが、その子の人格そのものを評価するという側面があるからです。●この、二人の先生が言っていることは、結局はいっしょなんだな。「大人は子供をよく見ていろ!」ということかな。
ちょっとしたことに対して、「おりこうさんねー」と人格全体を評価してしまうと、一回一回のことばの重みがなくなっていきます。「おりこうさん! スゴイ、スゴイ」というのが決まり文句のようになり、それが当たり前になると、ほめられないと逆に不安になったり、人からの評価に変に敏感になってしまう可能性が高くなります。
ほめること・しかることより大切なことは、子どもと同じ視線でものを見て、共感して、ことばをそえてやることです。たとえば、子どもがブロックで何かを一生懸命つくっていたとします。そして何とかつくりあげて、「お母さんできたよ!」と嬉しい気持ちでいっぱいの様子が伝わってきたとします。そのとき、その気持ちを子どものつもりになって代弁してやることなのです。(中略)
「あら、すごいのつくったのね!」
「やったね、こんな高いのよくできたね」
と子どもの気持ちを子どもにかわって表現してあげてほしいのです。また、失敗して、子ども自身が<くやしーい>と思っているなと伝わってきたときには、
「くやしいね」
「残念ね、次はがんばろう!」
と言ってやればいいのです。それが、”共に感じる(共感)”ということです。基本は、子どもはこんな気持ちでいるのだろうという、その気持ちを直感的に察することです。それをことばにする。<ママは僕を見ててくれて、同じように考えていてくれる>と感じることは、子どもが自信をもち世界を広げていく原動力になるのです。(p79〜80)
■ 高田渡 のライヴの話は、また明日(^^;;;「褒めること」について 2005/02/10
●先日、大人でも 褒められるとうれしい と書いたが、じつは 「褒めること」 はとても難しい。 『本の向こうに子どもが見えた』 吉井享一・著(エイデル研究所)¥1492 を読むと、こんなことが書いてある。
子どもについての考えかたで「子どもは、褒めてあげれば、やる気を起こす」というのがある。家庭教育の講演会などでは、必ずといっていい程言われることで、お母さん方の中にもこの見方への支持者は多い。
たしかに褒められて嫌な気になる人はいない。よくできたねと言われれば、自信がついてくるかもしれないし、お手伝いができてえらかったねと褒められたなら、これからもしようと思うだろう。
けれど、私は、「褒めれば喜び、やる気を起こす」というこの言い方が、とてもいやだった。なぜ、いやだったかというと、「褒める」ということを、子どもたちにやる気を起こさせるための「 て (方法・手段)として使う」ような考え方が好きになれなかったのである。「褒める」ということは、ためにすることではない。相手の行為なり、考え方、意見なりがすばらしいことに感動する。そのときの相手への賛辞が褒めるという行為になる。そこには、その賛辞によって相手が喜ぶとか、やる気を起こすだろうとかの計算ら下心はない。ただ、「いいなあ」という思いがあるだけだ。(中略)
子どもにとってうれしいのは、褒められることもそうだけれども、それ以上に、自分の努力をきちんと見ていてくれることである。掃除のたびに、いつも最後のゴミ捨てに行く子がいる。教師にとって大切なのは、その子を褒めることよりも、その子がそういうことができる子だということを、しっかり見知っておくことだろうと考えている。(p33)人間やっててほめられるのは、やっぱうれしい 2005/02/08
●ダイエットを始めて1ヵ月。ノコギリの歯のような体重変動グラフがずっと続いていたのだが、長期停滞傾向を最近ようやく抜け出して、日々少しずつ体重が減り始めた。こうなると、夜の「テルメ通い」にもますます力が入る。今夜も、伊那市医師会の会合から夜9時前に帰って「おとうさんは、これからテルメに行って走ってくるから、おかあさんと寝なさい」そう子供たちに言うと、天使幼稚園年長組に通う次男が振り返って、ぼくの顔をマジマジと見ながらこう言った。
「あれ? かお、こっちの横のほうから見たら、おとうさん、なんかちょっと痩せたね!」 うれしいこと言ってくれるじゃぁないか(^^;) 大人だって、褒められるとウレシイ。たとえ子供からだってね(^^;) 彼は、ぼくの日々の努力をきちんと評価してくれていたのだ。(単に、親に対して気を使っているだけなのかもしれないが……)何だか親子が逆転しているな(^^;;
そう言っておいて、次男は何か 片手落ちだったんじゃないか? と、ふと不安に感じたみたいなんだな。突然、母親の方を向いて、あわててこう付け加えたのだ。
「おかあさんも、さいきん、すこし 背が伸びたんじゃない?」 あははははは(^^)
『鰍沢』 六代目・三遊亭圓生 2005/02/06
●厳冬のこの時期、みなが寝静まった深夜に一人この 『鰍沢(かじかざわ)』 を聴くのはほんと怖い。ちょっと陰にこもった圓生さんの声がラジカセから響いてくるだけで、吹雪の鰍沢に迷い込んでしまった旅人その人になってしまうのだ。ものすごくリアルに、その光景が目に浮かび、寒さが体感される。
『江島屋騒動』 とちょっと似た話だけれど、「江島屋」が母親の怨念と入水した娘の幽霊の恨みが恐ろしい 怪談話 であるのに対し、 『鰍沢』 には幽霊は登場しない。死んでしまった人間よりも、生身の人間のほうがよっぽど怖いということか。 立川志らく 氏もこう書いている。
鰍沢の冬山で迷子になった旅人が泊まった小屋には、以前買った事がある花魁(おいらん)がいた。心中をして吉原から鰍沢に逃げてきたのだ。花魁は旅人を毒殺して持ち金を奪おうと考える。しかし失敗して亭主に毒を呑ませてしまう……(中略)●『鰍沢』は、明治の天才落語家、 三遊亭円朝 の作。同じく「円朝・作」の傑作 『死神』 を、三遊亭直伝で聴かせる 六代目・三遊亭圓生 版で、明日は聴いてみよう。
真冬のサスペンス落語。八代目林家正蔵の演ずる「鰍沢」がその任にあっていたのか、一番不気味であった。花魁が雪山の中、鉄砲を持って追い掛けてくる恐さは、スタンリー・キューブリック監督の 「シャイニング」 のクライマックス場面を彷彿とさせる。これは決して人情噺ではない。まさしくサスペンス落語ととらえるべきだ。
(『全身落語家読本』p177)
近ごろ読み聞かせした絵本 2005/02/04
●今日の昼休みは「いなっせ」7F「ちびっこ広場」での 子育て支援セミナー 。今回でたしか 12回目 。おぉ、1年間無事何とか続いたのだな。よく頑張ったものだ。今日のお題は 「予防接種について」 。今回の参加者は少なくて、7〜8人くらいだったか。それでも毎回聞きに来てくれるお母さんが何人もいて、ホントありがたいことです。
建前のはなしではなくて、本音を話させていただきましたよ。毛利子来センセイの悪口とか(^^;;
お終いに絵本を2冊読みました。今回は 不思議な絵本の特集 です。 『サーカスがやってきた』 と、 『ふしぎなナイフ』 の2冊。これ、1〜2歳児でも十分いけます(^^;)
●忘れないうちに、先週の火曜日に 美篶中央保育所 の内科健診のあと 年少組 で読んだ絵本のことも書いておこう。
1) 『マジック絵本』 今回の導入はこの絵本。「ちゃらら ららら〜♪ ちゃらららら、らーらら〜♪♪」と、 ポール・モーリア楽団 の「オリーブの首飾り」を口ずさみながら、マジシャンさながらに真面目くさって絵本のページをめくります。年長さん相手の時には、この絵本は通用しないのだけれど、年少さんはみな、目をまん丸くして不思議がってくれました(^^;) あはは、受けてよかった。
2) 『こんにちワニ』 中川ひろたか・文、村上康成・絵(PHP) 年少さんでも、あと2か月すれば 年中さん なので、ずいぶんと成長してるんだな。この 年長さん向き 「ことば遊び絵本」は、年少さんにも 大受け でしたよ。
3) 『わにわにのおふろ』 近頃しつこくこの絵本を読んでいます。だんだんと、この絵本を読む 「コツ」 が判ってきたゾ!
4) 『たまごにいちゃん』 あきやまただし・作絵(すずき出版)ワニつながりで 「ひまわに」 を読もうかととも思ったのだけれど。
5) 『こんにちワニ』 子供たちのリクエストで、もう一度読まされました(^^;;
小学校の先生方への講演 2005/02/02
●長野県教育委員会は、今年から新しい試みとして 小児科医・産婦人科医・皮膚科医など が学校に出向いて、授業をしたり講義をしたりする事業を始めた。ぼくも登録されたのだが、早速に 高遠小学校 からお呼びがかかった(^^;)
今日の水曜日の午後、3時半〜5時までの1時間半、教職員を対象に講演を依頼されたのだ。水曜日はどこの学校でもたいてい職員会議の日。ぼくも午後は休診にしているから、お互いに都合がいい。ただ、学校の先生を相手に話をした経験がないので(ちょうど3年前、伊那東小学校PTAからの要請で、授業参観の後に家庭科室で親御さんと先生方に講演をしたことはあったけれど)いったい、どんな話をすればいいのかずいぶんと悩んだ。
事前の打ち合わせで、高遠小学校の教頭先生は「えぇ。どのような内容でも構いません。先生が決めていただいて結構です」そうおっしゃってくれた。うれしかった。そこで今日は、前半で インフルエンザとノロウイルス感染症 の話をして、中盤で 「絵本の絵を読む楽しみ」 を、プロジェクターを使って解説し、お終いに 軽度発達障害 に関して個人的な感想を述べさせてもらった。なんだかまるで関係のない、まとまりのない話になってしまったが、何とか時間ぴったしに講演を終了することができた。いつも大抵、ぼくは指定時間内に話が終わらなくて、主催者に迷惑をかけているのだが、それだけは今日は大成功だったぞ(^^;;
終了後に校長室に呼ばれて、お茶をご馳走になったのだが、校長先生は 「絵本のお話が一番面白かった」 そう仰った。そうか、やっぱり「絵本の話」をしてよかったな(^^)
<先月の日記>へ
T O P ご案内 おとうさんの絵本 読書&CD Now & Then リンク 北原こどもクリニック

